目次
1.AIが職を奪う?仕事が変わる、2025年以降の職種予測
2.将来なくならない仕事ランキング
3.これから需要が増える仕事
4.今後、無くなると予想される職種
5.転職エージェントから見る職業選択のポイント
6.AIと共に生きる時代の考え方
7.【結論】2025年に生き残る職業の展望
8.最後に・・・
1.AIが職を奪う?仕事が変わる?2025年以降の職種予測
1.1 今後なくならない仕事の定義と重要性
2025年以降、AI(人工知能)の急速な進化により、私たちの働き方や職業のあり方は大きく変わろうとしています。ニュースやSNSでは「AIが仕事を奪う」といった不安を煽るような情報が飛び交っていますが、果たしてそれは本当なのでしょうか?
まず大切なのは、「すべての仕事がAIに奪われるわけではない」という前提です。むしろ、AIでは代替できない仕事や、新たに生まれる職種も存在します。今後なくならない仕事とは、単なる作業やルーチンではなく、人間にしかできない価値提供が含まれるものです。
たとえば、創造性を必要とするアート分野、対人関係に基づくケアや教育、複雑な意思決定を必要とするマネジメントやリーダーシップの領域などが挙げられます。これらの仕事は、AIが進化しても残ると考えられており、むしろAIの進化によってその重要性が高まる可能性さえあります。
「今後なくならない仕事」を理解することは、将来に備えたキャリア設計において非常に重要です。単なる就職・転職の手段ではなく、自分の人生そのものを築く基盤としての仕事をどう選ぶか。その判断軸が変化しているのです。
1.2 AIの進化と職業への影響
ここ数年、ChatGPTをはじめとする自然言語処理AIや、画像・動画生成AI、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの技術が急速に普及しています。この結果、以前は人間にしかできなかったと思われていた業務の一部が、すでにAIによって自動化されています。
具体的には以下のような職業・業務が影響を受けています。
- データ入力や請求処理などの定型的な事務作業
- 財務諸表の分析やリスク評価などの金融業務
- Webライティング、記事作成の一部
- 顧客サポート業務(チャットボットの活用)
- 製造業のライン作業の自動化
これらの変化は、単なる人員削減ではなく「仕事の中身そのもの」が変わることを意味しています。つまり、同じ職種名であっても、必要とされるスキルセットや価値の出し方が大きく変化しているのです。
こうした背景を踏まえ、求職者や転職者に求められるのは「変化を前提としたキャリア戦略」です。過去の経験だけに頼るのではなく、新たなスキルの習得や自分の適応力を高めることが、これからの時代には必須となるでしょう。
1.3 仕事選びの基準『年収と将来性は重要か?』
仕事を選ぶうえで、多くの人が重視するのが「年収」・「福利厚生」・「雇用の安定性」といった条件面です。確かにこれらは重要な要素ですが、AI時代においてはそれだけでは不十分です。
AIによる変革が進む中で注目すべきは、以下の3点です。
- 市場の将来性 :その業界や職種が5年後、10年後にも存在しているか?
- スキルの汎用性:他の分野にも応用可能なスキルが身につくか?
- 自己成長機会 :継続的にスキルアップができる環境か?
たとえば、今の時点で高年収の職種でも、将来的にAIによって需要が減少するリスクがある職業は、「一時的な高収入」として考えるべきです。一方、現在の年収が平均的でも、今後の成長が見込まれる分野に飛び込むことは、長期的なキャリア形成において非常に有利になります。
また、「やりがい」や「社会貢献度」といった内面的な価値観も、仕事選びにおいて無視できない要素です。特に人生100年時代といわれる現代では、長く働き続けることを前提とし、自分が納得できる仕事に就くことが、結果として幸福度や生産性の向上にもつながるのです。
2.将来なくならない仕事ランキング

2.1 医療従事者 ―看護士と医師の将来性―
医療業界は、テクノロジーの進化とともに大きな変革を迎えていますが、その中でも「人間ならではの判断」が必要な場面は依然として多く、特に看護師や医師といった職種は、将来にわたって高い需要が続くと考えられています。
AIがレントゲン画像の診断や投薬の提案などを行う事例は増えていますが、患者の心理的なケアや、突発的なトラブルへの柔軟な対応、複雑な病態の総合的な判断は、まだまだ人間の手に委ねられています。
また、日本は高齢化社会が加速しており、今後ますます医療・看護のニーズが高まることが予測されています。都市部だけでなく、地方においても看護師不足が深刻化しており、全国的に安定した雇用が期待できる分野です。
医療従事者の仕事は専門性が高く、一朝一夕に代替されることがないため、AI時代においても「人間の手で支える」職業の代表例といえるでしょう。
2.2 データサイエンティストとエンジニア ―技術職の進化―
AI時代を支える中核的な職業として、データサイエンティストやAIエンジニアといった技術職の重要性は今後ますます高まります。これらの職種は、単にプログラムを書くことだけでなく、膨大なデータを解析し、そこからビジネスや社会の意思決定に活かすという、戦略的な役割を担っています。
データ分析や機械学習、自然言語処理のスキルは、医療・金融・小売・製造などあらゆる業界に応用可能であり、その汎用性の高さも大きな強みです。また、リモートワークが可能なため、働き方の自由度も比較的高いという魅力があります。
このような職種に求められるのは、「論理的思考力」・「問題解決能力」・「継続的な学習力」です。技術の進化が早い分野であるため、常に最新の知識をキャッチアップし、柔軟に対応できる力が重要です。
2.3 営業職とカウンセラー ―人間の強みが活かされる職種―
AIが得意とするのは「データに基づいた判断」や「高速な情報処理」ですが、人間が得意とするのは「感情に寄り添うこと」や「文脈から空気を読むこと」です。このような人間ならではの能力が活かされるのが、営業職やカウンセラーといった職業です。
たとえば営業職では、顧客との信頼関係構築や、提案内容の柔軟なカスタマイズ、交渉力などが求められます。カウンセラーにおいては、クライアントの心の状態に寄り添い、非言語的なサインから心の機微を読み取る力が必要です。
これらはAIには代替が難しいスキルであり、今後も人間による対面の価値が再評価される可能性があります。特に、人と深く関わる仕事は、時代が変わっても決してなくならない重要な役割を担っていくでしょう。
3.これから需要が増える仕事

3.1 女性向け ―今後需要が高まる職種とは?―
少子高齢化やライフスタイルの多様化を背景に、女性が活躍できるフィールドもますます広がっています。特に育児や介護といった生活に密接に関わる分野では、女性ならではの視点や共感力が求められる場面が多く、社会的ニーズの高まりとともに新たな職業機会が生まれています。
たとえば、保育士や子育て支援アドバイザー、訪問看護師、産後ケア専門スタッフといった職業は、今後も安定的な需要が見込まれます。また、女性起業家としてオンラインを活用したビジネスを展開する人も増えており、SNSマーケターやWebデザイナー、動画編集者など、在宅ワークを可能とするクリエイティブ職も注目されています。
これらの職種は、家庭との両立が可能でありながらも専門性を高めてキャリアアップが可能な分野です。今後の働き方として「選択肢の広さ」と「柔軟性」は非常に大切な要素となるでしょう。
3.2 福祉と介護:社会での重要性と将来性
日本は急速な高齢化社会を迎えており、福祉・介護分野の人材需要は今後さらに高まっていくと予測されています。厚生労働省のデータによると、2025年には全国で約38万人の介護人材が不足すると見込まれています。こうした状況により、介護福祉士、ケアマネージャー、訪問介護スタッフなどの職種は、今後も安定した雇用と将来性を持つ「なくならない仕事」と言えるでしょう。
介護分野ではAIやロボット技術の導入も進んでいます。たとえば、移乗介助を補助するパワーアシストスーツや、見守りセンサーを活用した夜間監視など、テクノロジーは介護現場を効率化し、スタッフの負担を軽減しています。しかし、利用者との信頼関係を築いたり、認知症高齢者の情緒に寄り添った対応をしたりといった、「人間の温かみ」は決してテクノロジーでは代替できません。
また、福祉分野は社会貢献度が高く、働きがいを感じやすい職種でもあります。資格取得制度や研修制度も整備されており、未経験からキャリアアップを目指せる点も魅力です。安定性・社会的意義・将来性の3点から見て、福祉と介護は今後も重視される分野として注目されるでしょう。
3.3 クリエイターの役割 ―AIと共存する新たな市場―
クリエイティブ業界もAIの進出が著しい分野ですが、一方で人間にしかできない表現や発想力の重要性が再確認されており、クリエイターの役割は今後さらに進化していくと考えられます。たとえば、AIが生成した画像や音楽をベースに、最終的なアウトプットを人間が監修・編集するという「協業型」の制作プロセスが広がっています。
映像ディレクター、アートディレクター、UX/UIデザイナー、ゲームクリエイター、作詞家・作曲家など、創造性をベースとした職業は、AI時代においても高い価値を持ちます。特にストーリーテリングや文化的背景を考慮した演出は、現時点ではAIが不得意とする領域であり、今後も「人間らしさ」が求められるでしょう。
さらに、クリエイターは自身のSNSやYouTubeなどを活用して個人で発信し、収益を得る時代へと変化しています。これは従来の企業組織に属する働き方とは異なる「個人のブランディング」が鍵となる働き方であり、自由度が高く、多様なライフスタイルに適応できます。
AIとの共存を前提としながら、人間の感性・美意識・直感力を武器にすること。これがこれからの時代におけるクリエイターの生き方であり、競争優位を築く重要な要素となります。
4.今後、無くなると予想される職種

AIとロボティクスの急速な進化は、これまで人間が担っていた業務の多くを代替可能にしています。特にルーティン化された業務、マニュアル通りにこなせる作業は、自動化の対象となりやすく、今後減少する可能性が高い仕事といえるでしょう。
4.1 ルーティンワークが減少する職業
以下のような職業は、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)によって代替されつつあります。
- データ入力・事務作業
- 銀行の窓口業務
- 小売店のレジ係
- 電話オペレーター
- 定型的な法務・会計業務
これらの仕事は、決まったフォーマットに沿って処理することが多いため、AIにとっては比較的容易に処理できる分野です。特にクラウド型会計ソフトやAIチャットボット、セルフレジの普及などにより、業務量自体が削減されていくことが予測されます。
しかし、完全になくなるというよりも、”仕事の質が変わる“と考えた方が現実的です。たとえば、事務職の人材には、データ分析や業務改善の提案など、より高度な役割が求められるようになるでしょう。
4.2 自動化される業界の具体例
特定の業界では、AI・自動化による大規模な変革がすでに始まっています。以下は代表的な例です。
- 製造業 :組立ラインのロボット導入により、人手が不要になる工程が増加。
- 運輸業 :自動運転技術の進展により、トラック運転手やタクシー運転手の需要が減少傾向に。
- 金融業界:AIが融資審査や投資判断を自動で行い、アナリスト業務が縮小。
- 流通業 :倉庫内のピッキングや配送ルートの最適化もAIが担うように。
これらの業界では、業務の効率化とコスト削減が同時に求められているため、AI導入が加速しています。変化に対応できるよう、従業員にも新たなスキルの取得が求められます。特に運輸業のおける自動運転の進歩は実用段階にかなり近づいている状況です。近い将来、実証実験が進み高速道路での長距離運転から実用化されると思われます。
次に製造業の分野では、自動化(DX化)が進んでおり人とロボットの混在ラインが一般的になってきました。今後は設備保全やメンテナンスの分野にも自動化の導入が進み、ロボットがロボットをメンテナンスをする時代がやってくることが予想されます。
4.3 文系職での今後の課題と対策
文系出身者が多く就く職種――たとえば営業、事務、企画、編集など――も、AI化による影響を免れません。特に、リサーチ業務や資料作成、スケジュール管理といったサポート業務の自動化は進んでおり、定型的な業務の付加価値は下がっています。
一方で、文系人材にしかできない仕事も確実に存在します。例えば、
- ストーリーテリングやコンテンツ設計
- 顧客との信頼関係構築や深層ニーズの発掘
- 法律、文化、歴史などに基づいた考察と提案
文系出身者が生き残るためには、単なる事務処理能力ではなく、創造性や対人スキル、問題解決力といった“人間にしかできないスキル”を伸ばす必要があります。
また、近年では「文理融合」が求められており、文系でもプログラミングやデータ分析の基礎を学ぶことが推奨されています。業界や職種を問わず、「文系だからこそ活きる視点」をAI時代にどう応用していくかが、今後のカギとなるでしょう。
次の章では、こうした変化を踏まえ、転職エージェントが実際にどのようなアドバイスをしているのか、またAI時代に求められるスキルやキャリアの考え方について深掘りしていきます。
5.転職エージェントから見る職業選択のポイント

5.1 AI活用におけるスキルアップの実践法
転職エージェントが口を揃えて言うのは、「AIを恐れるのではなく、活用できる人材になること」が重要ということです。
以下のスキルは今後の職業選択において大きな武器になります。
- デジタルリテラシー:Excel、Googleツール、クラウドサービスの活用力
- プログラミング :Python、SQL、JavaScriptなど、初心者でも学べる環境は整っています
- AIツールの活用法 :ChatGPT、Notion AI、Canva AIなどを活用した業務効率化術
これらはすべて独学やオンラインスクールで習得可能です。
5.2 キャリアプラン ―長期的な視点で職業選択を考える―
キャリア選択において重要なのは、目先の収入や安定性だけではありません。以下のような「長期的な視点」で考えることが求められます。
- 自分の強みはなにか
- 10年後も存在する仕事か
- どんなスキルを積み上げられるか
- ライフスタイルとの相性は?
キャリアは「階段」ではなく「ジグザグ道」です。途中での転職やキャリアチェンジを前提としたプラン設計がカギになります。
5.3 就活生へのアドバイス ―適職診断の活用法―
学生や若年層には、「適職診断」「性格診断」などを有効に活用することを勧めます。ミスマッチによる早期退職は自信を失う大きな要因となります。近年は、AIを活用した精度の高い適職診断ツールが登場しており、自分の性格特性・価値観・スキルと職業とのマッチングを可視化してくれます。
<主なツール例>
診断結果はあくまで“参考”ですが、自分を客観視する大きなヒントになります。
こうしたツールを使うことで、「なんとなく向いていそう」・「人気だから」ではなく、自分に本当に適した職種・働き方を客観的に判断できるようになります。また、就活においても”AIリテラシー“が新たな強みとなっています。ChatGPTを活用した自己PR文の作成や、AIによる模擬面接など、デジタルネイティブ世代ならではの工夫が内定獲得につながるケースも増えてきました。
転職エージェントやキャリアカウンセラーと連携することで、自分の可能性を最大限に広げられるでしょう。
5.4 転職エージェントから見る職業選択のポイント
AIが社会全体に浸透している今、転職やキャリアチェンジを考える人にとって、どのような職業選択が有効なのかを判断するのは容易ではありません。そこで参考になるのが、転職エージェントの視点です。彼らは日々、多数の求職者と企業のニーズをマッチングしており、時代の変化に最も敏感に対応している職業のひとつです。
5.5 AI活用におけるスキルアップの実践法
転職エージェントが近年強調しているのは、「AIを使いこなす力」つまりリテラシーと実践力です。具体的には以下のようなスキルが求められています。
- データリテラシー :ExcelやBIツール(Tableau、Power BIなど)を使ったデータ分析能力
- プログラミング基礎:Python、SQLなどを用いた自動化や簡易ツール開発
- AIツールの活用力 :ChatGPT、Notion AI、Copilotなどのツールで業務を効率化する力
- 定義設定や質問力 :AIを利用する場合、定義設定や質問力によって情報の精度が大きく異なります
特に非エンジニア層にとっては、”難しいプログラムを書く“ことよりも、”AIで何ができるかを知り、適切に使う“ことのほうが重要です。転職エージェントは、こうしたスキルを持つ候補者が非常に人気であると指摘しています。
また、短期集中のオンライン講座やeラーニングを通じて、働きながら学ぶスタイルも主流となりつつあります。副業やプロボノでの実践経験を通じて、スキルを可視化することも効果的です。
5.6 キャリアプラン ―長期的な視点で職業選択を考える―
転職エージェントは短期的な転職支援だけでなく、「5年後・10年後の市場価値を高める」視点からのアドバイスも行っています。
- 市場価値を可視化する
どの業界・職種が今後も成長するのか、どんなスキルが汎用的なのかを知る。 - スキルの棚卸し
今の自分が持つ経験・資格・強みを再確認し、それをどう伸ばしていくかを考える。 - ライフスタイルとの調和
リモートワーク、ワークライフバランス、副業との両立など、自分に合った働き方の模索。
これらの観点から、自分のキャリアの“軸”を明確にすることが、変化の激しい時代においては非常に重要です。職種や業界が変わっても、その軸がぶれなければ、市場での信頼や自信を維持しやすくなります。
6.AIと共に生きる時代の考え方
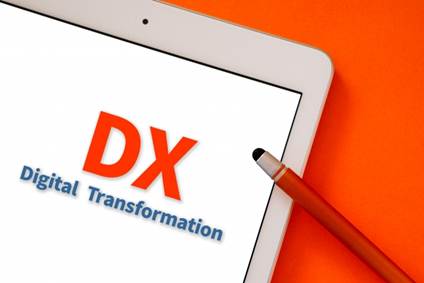
AIが社会や職業構造に与える影響は年々拡大していますが、だからこそ私たちは「人間にしかできないこと」に目を向け、キャリアの軸を再定義する必要があります。人間の価値は、単なる作業や効率では測れない、深く根源的な力にあります。
6.1 人間の価値をどのように見出すか
AIにできることと、人間にしかできないことの線引きが、今後の社会でますます重要になります。では、「人間の価値」とは何でしょうか?
それは、次のような要素に表れます:
- 創造性 :まったく新しいアイデアやアートを生み出す能力
- 共感力 :他人の立場に立って考え、感情を理解する力
- 倫理的判断 :ルールや利益を超えた「正しさ」に基づく意思決定
- 信頼関係の構築:人との関わりを通じた長期的な関係性の構築
これらは、AIには模倣できても、本質的には習得できない人間独自の強みです。たとえば、医療やカウンセリングの場面では、データ分析以上に「相手の感情に寄り添う力」が成果に直結します。
社会がAIに多くの作業を委ねるようになるほど、逆説的に、人間の持つ温もりや直感がより貴重になるのです。
6.2 心の力 ―AIにはないコミュニケーション能力の重要性―
テクノロジーが進化しても、人間同士の「心の通った対話」は常に求められ続けます。ビジネスにおいても、セールス、マネジメント、チームビルディングといった領域では、高いコミュニケーション能力が不可欠です。
- 言葉の選び方
- 空気を読む力
- 相手に安心感や信頼感を与える表情や声のトーン
こうした「非言語コミュニケーション」のスキルは、人間関係の潤滑油であり、チームの生産性や創造性にも大きく影響します。
特にリモートワークが浸透する今こそ、「会わずとも信頼される力」や「短い時間でも本質的な信頼を築く力」が求められています。これらは、一朝一夕で身につくものではありませんが、意識的な実践を通じて強化することができます。
6.3 今後の職業選択における自分の強みの把握方法
自分に合った仕事を選ぶには、「自分の強みを正しく理解する」ことが出発点です。これは、以下の3つの観点から掘り下げることが有効です。
- 過去の経験 :成功・失敗した場面で発揮された自分らしさを振り返る。
- 他者の評価 :同僚や友人、上司が自分について言っていた長所を洗い出す。
- 自己分析ツールの活用:ストレングスファインダーや16Personalitiesなどのツールで、客観的な視点を取り入れる。
また、強みは「得意なこと」だけでなく「好きなこと」にも現れます。やっていて疲れないこと、時間を忘れるほど没頭できること。それこそが自分の強みであり、キャリアの軸になり得るのです。
AIに仕事を奪われるかどうかを恐れるのではなく、「自分だからこそできる価値」を明確にすること。それが今後の時代を生き抜く最大の鍵となります。次章では、2025年以降に生き残る職業の展望と、それに向けて私たちが今から何をすべきかを具体的に紹介していきます。
7.【結論】2025年に生き残る職業の展望
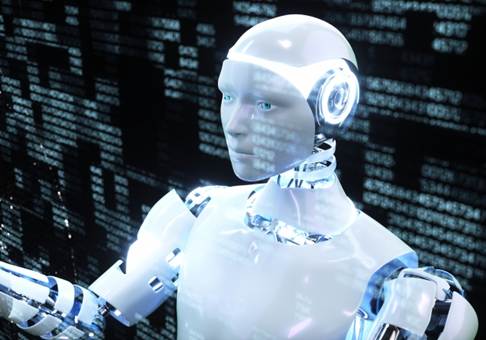
テクノロジーと人間の協働が加速する2025年以降の社会では、職業の「絶対的な安定」は存在しません。常に変化が求められる中で、重要なのは“何をするか”ではなく、“どう生きるか”という視点です。ここでは、未来に生き残る職業の特徴と、それに備えるための行動についてまとめます。
7.1 変化する社会に適応するために必要な行動
どんなに安定しているように見える職種でも、時代の波を乗り越えるには以下の行動が必要です。
- 継続的な学びを日常化する
一度身につけたスキルに満足せず、新しい知識・ツールに常に触れる姿勢が求められます。 - 複数のスキルを掛け合わせる
例えば「営業 × データ分析」や「看護 × AI活用」など、1つの分野にとどまらないスキルセットが強みになります。 - ネットワークと情報収集力を強化する
業界の変化をいち早くキャッチするには、人とのつながりや、正確な情報源を持つことが鍵です。 - 副業やプロジェクトベースの仕事に挑戦する
本業以外の活動からもキャリアを築く柔軟性が、時代に合った働き方となります。
変化を前提にした行動こそが、生き残る力そのものになります。
7.2 職種選びから見えてくる未来の可能性
2025年以降、生き残るとされる職種にはいくつかの共通点があります。
- 人間関係を基盤とする仕事(医療、教育、心理カウンセリングなど)
- 高度な判断や創造性を要する仕事(研究、アート、企画開発など)
- AIやデジタル技術と共存する職種(エンジニア、データサイエンティスト、DX推進担当など)
これらの職種では、単なる知識ではなく「課題解決力」や「チームと協調する力」が重要になります。そして、これらは職種を超えて応用できるスキルでもあります。
さらに、未来に向けて拡大する市場(例:再生医療、気候テック、メンタルヘルス分野など)にアンテナを張っておくことで、新たな可能性をつかみやすくなります。
7.3 継続的なスキルアップが求められる時代の到来
今後は「学び続けられる人」と「学びを止めてしまう人」で、大きな格差が生まれます。特に、以下のスキル領域は中長期的に重要視されます:
- デジタルリテラシー :AI、クラウド、IoTなどに対する基本的理解と応用力
- 問題解決力とクリティカルシンキング :複雑な課題を分解し、最適解を導く思考力
- 感情知性(EQ)とチームマネジメント :人と人をつなぎ、成果を最大化する力
- セルフマネジメントと柔軟性 :変化の中でもストレスに対処し、自分を律する能力
これらのスキルは一朝一夕には身につかないものの、日々の仕事や学習、実践を通じて徐々に培っていける力です。
未来の職業は、与えられるものではなく、自ら築き上げていくもの。だからこそ「学び続ける姿勢」そのものが、最大のキャリア資産となるのです。
8.最後に・・・
AIやテクノロジーの進化は、私たちの働き方や職業選択に大きな変革をもたらしています。しかし、だからといって「職を奪われる恐怖」にとらわれる必要はありません。重要なのは、自分自身の強みを見つめ直し、変化に柔軟に対応し続けることです。
2025年以降の社会では、「人間らしさ」がこれまで以上に価値を持ちます。創造性や共感力、倫理的判断といったAIには代替できない部分を磨きながら、AIやデジタルツールを活用して自分の能力を最大限に発揮することが求められます。
また、継続的な学びとスキルアップを習慣化し、多様な働き方や新しい挑戦に積極的に取り組む姿勢が、生き残るための大きな鍵となるでしょう。
未来は予測できない部分も多いですが、自分の価値を信じ、学び続けることで、どんな変化にも柔軟に対応できるキャリアを築いていけます。
そんな時代だからこそ、
株式会社S.I.Dは求職者ひとりひとりの ――心のサポート―― にもっとアプローチをしていきたいと考えています。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
これからの時代を生き抜く皆さんが、
自分らしく輝き続けることを心より応援しています。









