目次
1.面接ブッチ・入社辞退ドタキャンはなぜ多いのか?
2.まずは原因を知る。若者の置かれている環境要因とは
3.では、なぜ20代に多いのか?
4.面接を「だるい」「面倒」と感じる背景
5.面接ブッチ(無断欠席)が引き起こすリスク
6.企業が取り組める対策・施策
7.最後に・・・
1.面接ブッチ・入社辞退ドタキャンはなぜ多いのか?

採用担当者の方なら、一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
応募者はいるのに面接に来ない、内定を出したのに入社日に現れない──。特に20代の若手に多く見られる現象です。
こうした「面接ブッチ」「入社辞退ドタキャン」は、採用計画に大きな影響を与えます。面接官の時間や会社のリソースが無駄になるだけでなく、現場の人員計画にも影響し、場合によっては営業計画やプロジェクト進行にも支障をきたすことがあります。
では、なぜ20代の一部は「面接に行くのがだるい」「辞退を伝えるのが面倒」と感じてしまうのでしょうか。本記事では、その背景を社会的・心理的な要因から解説し、さらに企業側が取り組める具体的な対策を紹介します。
2.まずは原因を知る。若者の置かれている環境要因とは

考えられる環境的要因は主にこれら4つと言われています。
2.1 対人ストレス回避の心理
- 断るのが怖い・気まずい
「辞退します」と一言言うだけで済むのですが、本人にとっては「相手を怒らせるのではないか」「迷惑をかけてしまうのでは」と強い不安を感じるケースがあります。
結果として、逃げる(無視する)ことが一番ラクだと無意識に選んでしまう。 - 対人経験の不足
メールやSNSでのやりとりが中心で「直接断る」経験が少ない世代は、断ること自体に大きなハードルを感じやすい。
このように、「断る勇気の欠如」と「対人ストレス回避」がブッチの根底にあります。
2.2 選択肢過多と「試し応募」文化
求人が豊富で、IndeedやLINE応募のようにワンクリックで応募できる時代です。求人サイト側でも一括応募のボタンで10件、20件まとめて応募することが出来、返信(リアクション)のあった企業の中から初めて求人条件を確認している人も多く存在しています。
「とりあえず応募」→「気が変わったけど断るのも面倒」→「放置」という流れが起きやすい。
特に20代は「まだ他にいい会社があるかも」という気持ちが強く、内定や入社約束を“保険”扱いする人も少なくありません。
2.3 キャリア観・責任感の未成熟
20代前半は社会人経験が浅く、責任や契約に対する意識が十分に育っていません。
- 「合わなければやめればいい」というアルバイト的な感覚が残っている。
- 内定承諾や入社予定を、契約や信頼関係よりも「自分の自由な選択」として捉える。
- 結果、他社に決まった場合に「前の企業を放置」する行動につながる。
社会的な責任感よりも、「自分の気持ちを優先する」傾向が強いのが特徴です。
2.4 SNS・オンライン文化の影響
SNSの普及は人との距離感を変えました。
- ネット上では嫌な相手をワンクリックで切れる。
- この感覚を現実の人間関係にも持ち込み、**「無視でも大丈夫」**と錯覚する。
- 誠実に断るよりも「自分が嫌な思いをしない」ことを優先する。
つまり、無視することへの罪悪感が薄れているのです。
3.では、なぜ20代に多いのか?
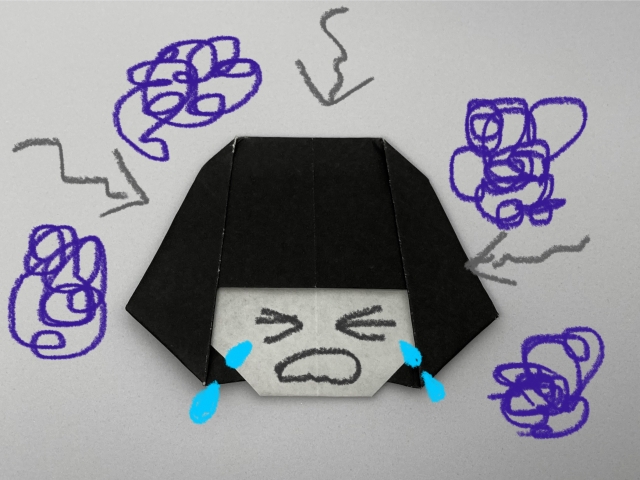
現在の若者は学生時代に「コロナ渦」を経験しており、それが大きな背景要因の一つになっています。
コロナ禍で大学生活を送った20代前半の世代は、特に 「対面での人間関係づくり」や「直接コミュニケーション」 の経験が乏しいまま社会に出ています。その影響が「面接ブッチ」や「辞退連絡を避ける行動」に直結しているケースは少なくありません。
具体的には、
- オンライン授業中心
→ 授業・ゼミ・サークルでの対面交流が激減し、人前で話す経験や対人トラブルを乗り越える経験が不足。 - アルバイトやインターン機会の減少
→ 接客やチームで働く場が制限され、「断る・謝る・相談する」といった実践的な対人スキルが育ちにくかった。 - 「会わなくても済む」環境に慣れた
→ ZoomやSNSで完結する生活に慣れ、嫌なことは「既読スルー」「未返信」でやり過ごす癖がついた。 - 不安感の増大
→ 対面に慣れていないため「面接官に会う=怖い」「断る=嫌われる」と心理的ハードルが過剰に高く感じられる。
つまり、コロナ禍世代の若者は 「断るスキルを学ぶ場」や「小さな失敗を経験する場」 を失ってきたため、採用の現場で「連絡できずに逃げる」という形で表面化しているのです。
- 就職市場が売り手優位で「辞退しても他がある」という安心感が強い。
- 社会経験が浅く、断り方のマナーを学ぶ機会が少ない。
- SNS的な“既読スルー文化”が染みついているため、黙って消えることに心理的抵抗が薄い。
「辞退します」と言えない思考回路の例
- 「断ったら怒られるかも → じゃあ言わない方が安全」
- 「自分ひとりが連絡しなくても大丈夫でしょ」
- 「もう会うことないし放置でいいや」
- 「後で言おう」→ 面倒になって放置
3.1 社会的に見た問題点
- 企業側は採用計画に大きな支障が出る。
- 結果として 「若手は信用できない」 という偏見につながり、真面目な求職者まで不利益を被る。
- 長期的には本人にとっても「逃げグセ」がつき、キャリア形成にマイナス。
これは**20代の一部に見られる「回避行動」+「責任意識の希薄さ」**の表れです。
本当は「一言辞退します」と言えた方が自分の評価を下げずに済むのですが、本人にとっては「言うことの方が怖い・面倒」なので、逃げる方を選んでしまう。
4.面接を「だるい」「面倒」と感じる背景

面接を「だるい」「面倒」と感じる人の理由は様々ですが取りまとめると大きく以下の内容にまとめられます。
4.1 モチベーションの低下
- 低い志望度
多数の企業にエントリーした結果、第一志望ではない企業の選考に対するモチベーションが低下するケースです。
- 応募後の価値観の変化:
応募した時点では興味があったものの、時間が経つにつれて別の企業への志望度が高まったり、仕事内容への関心が薄れたりすることもあります。
4.2 面接への不安や自信のなさ
- 準備不足
面接対策や自己分析が十分にできていないと感じ、自信がないまま面接に臨むことへのストレスがあります。 - 面接慣れしていない
面接での受け答えに不安があり、緊張から逃げたいという心理が働きます。 - 過去の失敗経験
面接に落ち続けた経験から、再び同じような経験をするのが嫌だと感じる人もいます。
4.3 合理的・効率的な思考
- 「コスパ」の悪さ
転職活動全体を「面倒くさい」と感じ、特に志望度の低い企業のために時間や労力を費やすことに「コスパが悪い」と感じる若者がいます。 - 「タイパ」(タイムパフォーマンス)重視
効率を重視するあまり、企業研究や面接対策に時間をかけることに抵抗を感じることがあります。
4.4 情報過多による疲労
- 選考疲れ
多くの企業にエントリーし、それぞれの面接対策やスケジュール調整を行うことに疲れを感じてしまいます。 - 企業情報への不信感
企業のウェブサイトや採用情報だけでは実態が見えづらく、面接官の対応などからネットの評判や噂を信じてしまうことがあります。
この情報化社会の中で、求人サイトも多数ありスカウトメールやダイレクトメールなど複数のサイトから求人情報が個人に向けられ毎日のように送られる中で、「故意」でなくても「どの求人に応募したのか忘れる・分からなくなる」といったこともあります。構造的にすべてを対応することが難しい環境にもあります。
5.面接ブッチ(無断欠席)が引き起こすリスク

5.1 面接ブッチ(無断欠席)が引き起こすリスク
面接ブッチは手軽な選択肢に感じられますが、将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
● 将来の選択肢が狭まる
企業側でも過去の応募者情報を一元管理している企業が多くなっており無断欠席した企業には再応募できないのが基本です。
たとえグループ会社や関連会社での選考だとしても影響が出る場合があります。
● 大学や学校への信頼低下
大学推薦で応募している場合、無断欠席が学校やゼミの信頼を損なう可能性があります。
● 社会人としての評価の低下
連絡なしの無断欠席は、社会人として基本的なマナーが備わっていないと見なされます。
5.2 面倒な気持ちを乗り越えるための対策
●「スカウト系転職サイト」の活用
企業側からのスカウトを待つことで、自分で求人を探す手間を省けます。興味を持たれた企業から連絡が来るため、書類選考が免除されたり、最終面接が確約されたりするケースもあります。
● 自己分析ツールの活用
AIが志望動機を自動作成してくれるツールなどを使い、効率的に面接対策を進められます。
● 不安の原因を特定する
面接が怖い、不安だと感じる原因を明確にし、それに対する対策を講じることで前向きな気持ちになれます。
面接対策の効率化
面接でよく聞かれる質問や逆質問のテンプレートを用意しておくなど、準備の負担を減らす工夫も有効です。
辞退する際は必ず連絡する: 面接に行きたくないと感じたら、無断欠席ではなく、必ず電話で丁寧に辞退の連絡を入れましょう。社会人としてのマナーを守ることが、後のトラブルを防ぎます。
6.企業が取り組める対策・施策

6.1 応募時からのコミュニケーション強化
- 応募後の即時レスポンス
応募したらすぐに「応募ありがとうございます、◯日までに日程調整をお願いします」という自動返信+人のフォロー。
反応が遅いと候補者の温度感が下がりやすい。 - こまめなリマインド
面接前日・当日にリマインドメールやSMSを送る。LINEなど求職者が普段使う媒体を活用すると効果的。
6.2 選考フローの「軽量化」
- ワンクッション面接を導入
一次選考をオンライン・短時間で実施し、まず「会うハードル」を下げる。
→ ブッチ率を減らし、「とりあえず参加」してもらう。 - 選考スピードを上げる
20代は決断が早い会社に流れやすい。応募から内定までが長いと途中離脱やブッチが増える。
フローを軽量化することは、求職者との接点回数が増えるため多くのヒアリングの機会を設ける事が出来るため、無断辞退を防ぐのには効果的ですが一方で「管理工数(時間)」の掛かる作業となります。結果、労務コストが上がるため専任の担当者を設けたり、外注化する企業も増えつつあります。
6.3 応募者の心理的負担を下げる仕組み
- 「辞退フォーム」の設置
「辞退します」の一言すら言いづらい人向けに、ワンクリックで辞退できるフォームやボタンを用意。
(Indeedや自社採用サイトに設置可能) - 辞退を悪としないメッセージ
「やむを得ず辞退する場合も遠慮なくご連絡ください」と応募段階で伝えておくと、逃げずに辞退しやすい。
6.4 候補者理解の徹底
- 応募者アンケートや事前ヒアリング
志望度・転職理由・他社状況を事前に把握しておく。志望度が低い人はブッチ予備軍。 - 候補者ペルソナに合わせた対応
20代なら「スピード感・丁寧な説明・安心感」を重視。40代なら「条件・安定性の明確さ」を重視、など。
6.5 採用広報・ブランディングの工夫
- “信頼できる会社”の印象づけ
求職者にとって「怖そう」「堅苦しい」と思われると辞退連絡をしづらい。
社風・働き方・社員の声を出すことで、連絡しやすい心理的安全性を高められる。 - 採用ページや求人票で辞退ルールを明記
「辞退の場合は必ずご連絡ください。ご連絡いただければ柔軟に対応します」と書くだけでも抑止力になる。
6.6 データ分析と歩留まり改善
- どの求人媒体からブッチが多いか分析
媒体や応募経路で傾向が出ることが多い。ワンクリック応募の比率が高い媒体は、リスク管理が必要。 - 面接参加率・入社率をKPI管理
「応募数」より「面接出席率」「内定承諾率」を重視して改善施策を回す。
6.7 最終的なリスクヘッジ
- 複数人採用計画
「辞退・ブッチは一定数あるもの」と前提に、余裕を持った採用計画を立てる。 - 紹介会社・リファラル採用の活用
信頼関係を介した応募者は、ブッチ率が極端に低い。
企業側ができるのは、
- 「断りやすさ」を整えて 逃げるよりも連絡する方がラク にする
- 「心理的な安心感」を与えて 連絡しても大丈夫だと思わせる
- データ分析して 無断辞退の多いポイントを絞って改善
こうした工夫で、ブッチ率は確実に減らせます。
7.最後に・・・
20代に多い面接ブッチ・無断辞退は、回避行動+責任意識の希薄さ+環境要因が絡み合って生じています。
しかし、企業側が「断りやすさ」「心理的安心感」「スピード感」を整備すれば、確実に減らすことが可能です。
採用は「企業と候補者の信頼関係づくり」。
一方的に「若者が悪い」と批判するのではなく、候補者が行動しやすい仕組みを用意し、双方にとって気持ちの良い採用活動を実現していくことが重要です。
株式会社S.I.Dでは、求職者・転職者・就活生に向けた有意義な情報を配信しています。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
バックレやブッチは癖になります。プライベートで行えば友人関係が壊れ、
企業活動で行えば社会人としてのモラルや品格が疑われます。









