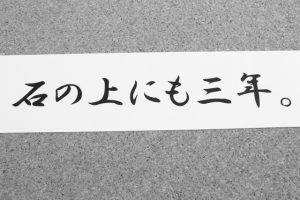目次
1.面接におけるSDS法とDESC法の基本理解
2.面接での活用場面
3.それぞれのフレームワークのデメリット
4.効果的な練習方法とフィードバック
5.最後に・・・・
1.面接におけるSDS法とDESC法の基本理解
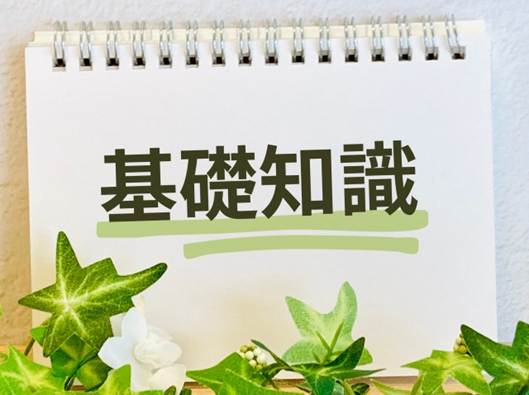
面接という場は、わずかな時間で自分の魅力や経験を最大限に伝える“プレゼンテーションの場”です。どれだけ優れたスキルや実績を持っていても、伝え方が整理されていなければ評価されにくいのが現実です。そこで効果を発揮するのが「SDS法」や「DESC法」といったフレームワークを活用した話し方。これらを使いこなすことで、話の構成に説得力が生まれ、面接官の印象に残りやすくなります。
1.1 SDS法とは?その特徴とメリット
SDS法とは、「Summary(要約)」「Detail(詳細)」「Summary(まとめ) 」の頭文字を取ったプレゼンテーション技法です。
簡単に言えば、「結論 → 理由・具体例 → 再度結論」で伝える方法です。
例えば、自己PRをSDS法で話すと次のようになります。
例:
- Summary(要約)
「私は課題解決力に強みがあります。」 - Detail(詳細)
「前職では業務改善プロジェクトを担当し、在庫管理システムを見直すことで作業効率を20%改善しました。」 - Summary(まとめ)
「この経験を活かして、貴社の業務プロセス改善にも貢献できると考えています。」
SDS法の最大のメリットは、「相手が理解しやすい構成」になる点です。特に面接官が複数人いる場合や、短時間で多くの質問を受けるような場面では、論理的でわかりやすい話し方が強い印象を残します。
また、最初に結論を伝えることで、面接官が“何について話すのか”を理解しやすくなるため、話の意図がズレにくくなるという利点もあります。
1.2 DESC法とは?その概要と利点
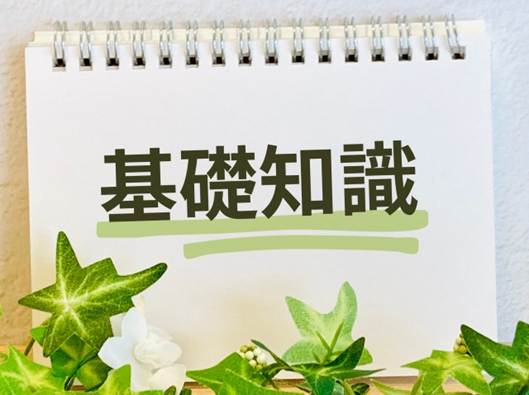
DESC法は、「Describe(描写)」「Express(表現)」「Specify(提案)」「Choose(選択)」の頭文字を取ったコミュニケーション技法で、主に対人折衝や意見対立の場で使われる方法です。
このフレームワークは、感情的にならずに相手と建設的な会話をするための手順を整理したもので、面接では意見の違いをスマートに伝える場面や、退職理由・転職理由を説明する際に非常に有効です。
例:前職を辞めた理由を聞かれた場合
- Describe(描写):「前職では少人数のチームで複数業務を並行して進めていました。」
- Express(表現):「業務改善提案をしても実行に移す機会が限られており、自身の成長機会に課題を感じました。」
- Specify(提案):「より裁量を持って提案や改善活動に取り組める環境を求めています。」
- Choose(選択):「御社のように若手にも意見を尊重し、挑戦を促す社風の中で力を発揮したいと思います。」
DESC法の強みは、ネガティブな話題を前向きに転換できる点です。転職理由や失敗経験を語るときでも、「感情的・否定的」にならず、「建設的・論理的」に伝えられます。
1.3 SDS法とDESC法の違いを整理する
| 比較項目 | SDS法 | DESC法 |
| 主な目的 | 論理的で簡潔に伝える | 感情を整理し、建設的に意見を伝える |
| 構成要素 | 要約 → 詳細 → 要約 | 描写 → 表現 → 提案 → 選択 |
| 活用場面 | 自己PR・志望動機・成果説明 | 退職理由・人間関係・問題対応 |
| メリット | 短時間で印象を残せる | 誠実さ・人間性をアピールできる |
| 注意点 | 内容が薄いと抽象的になりがち | 長くなりすぎると冗長になる |
どちらか一方を使えば良いというわけではなく、話す内容に応じて使い分けることが面接成功の鍵です。
1.4 PREP法とは?他のフレームワークとの比較
PREP法は、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(具体例)」「Point(再結論)」で構成される伝達法で、SDS法とよく似ています。
違いは、理由を明確に述べる点です。
SDS法は要約重視、PREP法は説得重視といえます。
例:志望動機(PREP法)
- Point :「私は御社の新製品開発に携わりたいと考えています。」
- Reason :「自分のアイデアを形にできる環境を求めており、御社の開発体制に共感したためです。」
- Example :「前職では顧客の要望を分析し、改良案を提案したことで新規受注率が15%上がりました。」
- Point :「この経験を活かし、御社でもユーザー視点の開発に貢献したいです。」
PREP法は営業職や企画職など、説得力を重視する職種で特に有効です。
1.5 面接におけるフレームワークの役割
フレームワークの目的は、「あなたの考えを整理し、相手に正確に伝える」ことです。
つまり、話の“型”を使うことで、自信を持って話せるようになるのです。
特に転職者の場合、面接官が知りたいのは「論理的思考力」「自己理解の深さ」「再現性のある行動力」です。
SDS法やDESC法を使えば、これらを自然にアピールできます。
2.面接での活用場面

2.1 具体的なシーンごとの使い分け
| 面接シーン | 適したフレームワーク | 目的 |
| 自己紹介 | SDS法・PREP法 | 印象的に自分を伝える |
| 自己PR | SDS法・PREP法 | 実績を簡潔に伝える |
| 志望動機 | PREP法 | 一貫性・熱意を見せる |
| 退職理由 | DESC法 | ネガティブ要素をポジティブに変える |
| 困難克服体験 | DESC法 | 問題解決力と対人対応力を示す |
2.2 自己PRにおける活用法
自己PRは、SDS法を使うと整理された印象を与えられます。
大切なのは「強み → 具体例 → 強みの再確認」という流れです。
例文:
「私は計画的に物事を進める力に自信があります。(Summary)
前職では新規プロジェクトのスケジュール管理を担当し、メンバーの進捗を可視化する仕組みを導入しました。その結果、納期遵守率が90%から98%に向上しました。(Detail)
この経験を通じ、チーム全体の成果を引き上げるマネジメント力を身につけました。(Summary)」
2.3 志望動機説明時の効果的なフレームワーク
志望動機ではPREP法が特に有効です。
「結論 → 理由 → 具体例 → 結論」で構成することで、一貫したストーリーを作れます。
さらに、SDS法を組み合わせて「志望動機 → 強み → 活かし方」を展開すると、面接官の納得感が増します。
2.4 面接官との対話をよりスムーズにする方法
DESC法は、質問に対して冷静に対応したい場面に効果的です。
たとえば、「前職の上司との関係が悪かった」といった質問にも、DESC法を使えば誠実かつ前向きに答えられます。
「Describe:チームで方向性の違いがありましたが、
Express:相手の考えを尊重しつつ、改善提案を伝えるよう努めました。
Specify:最終的には意見交換の場を設けて解決できました。
Choose:その経験から、今後も対話を重視して働きたいと考えています。」
3.それぞれのフレームワークのデメリット
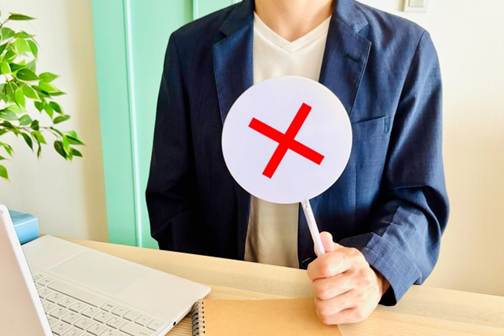
3.1 SDS法の注意点と悪い例
SDS法(Summary・Detail・Summary)は、話を「簡潔に・わかりやすく」伝えるのに非常に優れたフレームワークです。しかし、その反面で**「内容が浅くなる」「印象に残りにくい」**という落とし穴もあります。とくに転職面接のような短時間勝負の場面では、結論だけを繰り返しても、面接官の心には響きません。
3.2 「結論の繰り返し」だけでは中身が薄い
悪い例としてよく見られるのが、次のようなパターンです。
悪い例:
「私はコミュニケーション能力があります。人と話すのが得意です。これからもその力を活かしたいです。」
このように、要約(Summary)だけを並べているケースでは、どんな場面で・どのように発揮したのかがわからず、説得力がまったくありません。
面接官は「それは本人の感想なのか?」「根拠となる実績はあるのか?」という疑問を持ってしまいます。
3.3 Detail(詳細)の“厚み”がカギ
SDS法では、真ん中の Detail(詳細) 部分が最も重要です。
このパートに「数字・行動・背景・成果」などの具体的要素を入れることで、話が一気にリアルになります。
改善例:
「私はコミュニケーション力に強みがあります。(Summary)
前職では営業事務として、営業担当と顧客の間に入り、要望調整や納期交渉を行っていました。特に納期トラブル時には、顧客への説明を自ら担当し、クレームを未然に防いだことで、担当顧客の継続率が95%を超えました。(Detail)
この経験を通じて、状況を整理しながら相手の立場を理解する力を磨いてきました。(Summary)」
このように「数値化された成果」「具体的な場面」「自分の役割」を入れることで、面接官は“実際の行動”をイメージできます。
3.4 よくある失敗と回避法
| 失敗パターン | 問題点 | 改善のポイント |
| 結論だけの繰り返し | 根拠がなく印象が薄い | 「具体的な状況」+「成果」+「自分の行動」を入れる |
| Detailが長すぎる | 結論がぼやける | Detailは1~2エピソードに絞る |
| Summaryが抽象的 | メッセージが伝わりにくい | 最後のSummaryで「何を伝えたいのか」を再確認する |
3.5 SDS法を使うときのコツ
- 1分以内でまとめる意識を持つ:冗長になるとリズムが崩れ、聞き手が飽きる。
- 1つのテーマに絞る:複数の強みを同時に話すと印象が分散する。
- 「数字」と「結果」で締める:面接官の記憶に残りやすい。
SDS法は“構成の型”であり、あなたの行動や成果を引き立てる器です。
型に頼りすぎず、「相手に何を感じ取ってほしいか」を意識して話すことが、成功のポイントです。
3.6 DESC法のデメリットと課題
DESC法(Describe・Express・Specify・Choose)は、対人関係の摩擦を円滑にし、誠実さを伝えるフレームワークです。
特に退職理由や意見の衝突など、“ネガティブな話題”を説明する際に役立ちますが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。
3.7 話が長くなりすぎるリスク
DESC法は4つの段階を丁寧に踏むため、1つの回答が長くなる傾向があります。
その結果、面接官が途中で意図を見失ったり、「結局、何を伝えたいのか」が曖昧になるケースも多いです。
悪い例:
「前職では上司との意見が合わないことがあり、業務の進め方に課題を感じていました。改善案を出したり、ミーティングを提案したりしましたが、最終的にはあまり状況が変わりませんでした。そのため、もっと自分の意見を生かせる環境を求めて転職を考えました。」
この話し方だと、「感情の整理」「自分の成長」「相手への配慮」が見えず、単に愚痴っぽく聞こえてしまう恐れがあります。
3.8 感情を抑えすぎると“無機質”に聞こえる
DESC法は冷静で理論的な構成が魅力ですが、感情を抑えすぎると「熱意がない」「人間味が薄い」と受け取られます。
特に面接では、“ポジティブな姿勢”や“前向きな感情”を見せることが評価されるため、適度な感情表現が必要です。
改善例:
「Describe:前職では新しいシステム導入をめぐり、上司との意見の違いが生じることがありました。
Express:ただ、チーム全体がより効率的に動けるようにしたいという気持ちが強く、自分の提案をどう伝えれば理解してもらえるかを考えました。
Specify:その結果、上司と1対1で話す場を設け、意見交換を重ねることで一部の改善案を採用してもらえました。
Choose:この経験から、“自分の意見を押し通す”のではなく、“相手と歩み寄りながらより良い結果を導く”ことの大切さを学びました。」
このように、感情を添えながら「学び」や「成長」を伝えることで、DESC法に“人間味”と“説得力”が加わります。
3.9 DESC法でやってはいけないNG回答
| パターン | 問題点 | 改善策 |
| ネガティブな原因ばかり話す | 責任転嫁と受け取られる | 最後に「得られた学び」や「次にどう活かすか」を入れる |
| 相手批判になっている | 協調性がない印象を与える | 相手を尊重する表現に変える(例:「意見が異なる」など) |
| 結論が曖昧 | 面接官が意図をつかめない | Chooseの段階で明確な“今後の方向性”を伝える |
3.10 DESC法を成功させる3つのポイント
- 事実と感情を分けて話す:Describeでは感情を入れず、Expressで初めて自分の気持ちを述べる。
- Chooseで前向きに締める:「今後は〜を活かしていきたい」とポジティブに結ぶことで、印象が良くなる。
- 感情を“コントロール”して伝える:「悔しかった」「やりがいを感じた」など、自然な表現でOK。
DESC法の本質は「誠実な自己開示と建設的な姿勢」です。
単に問題を説明するのではなく、「どんな課題にどう向き合ったか」「その経験を今後にどう生かすか」を意識して話すことで、あなたの人間性・成長力・再現性が伝わります。
SDS法とDESC法はどちらも「伝える技術」を磨くための強力なツールですが、“型通りに話す”だけでは不十分です。
重要なのは、型を活かしながら「自分のエピソードを深く掘り下げる」こと。
SDS法では「成果を数字で」「背景を具体的に」。
DESC法では「感情を整理し」「学びで締める」。
この2点を意識すれば、あなたの言葉はよりリアルに、そして力強く面接官の心に響くはずです。
フレームワークを“守る”のではなく、“使いこなす”こと。それが、面接での成功を引き寄せる最短ルートです。
4.効果的な練習方法とフィードバック

4.1 実際のシミュレーションでの練習方法
フレームワークを身につける最短ルートは「声に出して練習すること」です。
鏡の前や録音アプリを使って、自分の話し方を客観的に確認してみましょう。
特におすすめは「1分間自己PR」「3分間志望動機」のように時間制限を設ける練習。
短時間で的確に話す力が鍛えられます。
4.2 フィードバックを活用する際のポイント
自分だけで練習するのではなく、第三者に聞いてもらうことが重要です。
友人やキャリアアドバイザー、模擬面接の担当者から、「伝わりやすかったか」「印象に残ったか」を具体的に聞きましょう。
フィードバックでは、「内容」よりも「伝わり方」「話す順序」「言葉選び」に注目することが上達の鍵です。
4.3 トレーニングの重要性とステップ
- 台本作成:SDS法やDESC法のテンプレートに沿って文章化。
- 音読練習:声に出してリズムや抑揚を確認。
- 録音・修正:客観的に聞いて改善点を洗い出す。
- 第三者評価:他人の視点からわかりやすさを確認。
- 本番想定練習:制限時間内で自然に話せるように調整。
この5ステップを繰り返すことで、どんな質問にも柔軟に対応できる“話しの型”が身につきます。
4.4 面接成功のためのまとめとポイント
- 面接は「内容」だけでなく「伝え方」で評価が変わる。
- SDS法・DESC法・PREP法を使い分けることで、論理的かつ人間味のある回答ができる。
- フレームワークを使えば、緊張しても話が整理しやすく、自信を持って臨める。
- 練習とフィードバックの積み重ねが、最終的な合格率を大きく左右する。
5.最後に・・・・
面接は“採点の場”ではなく、“あなたの考えを共有する場”です。
SDS法で構成を明確にし、DESC法で人間的な誠実さを伝え、PREP法で説得力を加える。
これらをバランスよく使うことで、あなたの経験や価値観は確実に面接官に伝わります。
大切なのは「型に頼る」のではなく、「型を使いこなす」こと。
自分らしい言葉で話すことが最終的な魅力になります。
もし面接で緊張して言葉が詰まっても、フレームワークを思い出してください。
それがあなたの“話す地図”となり、堂々と自分を表現する力になります。
株式会社S.I.Dでは転職の際に有意義な情報を定期的に配信しております。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
あなたの面接が、自信と納得のいく結果につながりますように。