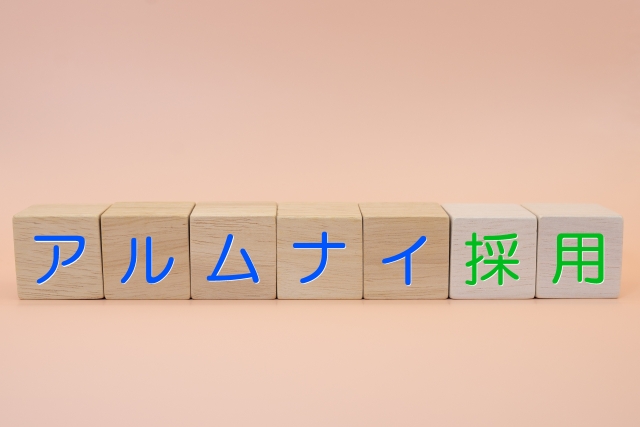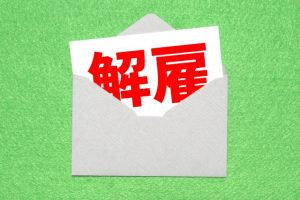目次
1.アルムナイ制度とは?概要とその背景
2.アルムナイ制度のメリットとデメリット
3.アルムナイ制度を導入する企業の実態
4.アルムナイ採用のプロセスと方法
5.アルムナイ制度導入のステップ
6.アルムナイ制度の未来と展望
7.最後に・・・
1.アルムナイ制度とは?概要とその背景
1.1 アルムナイ制度の語源と歴史
「アルムナイ(Alumni)」とは、もともとラテン語で「卒業生」を意味する言葉です。英語圏では大学や学校の卒業生ネットワークのことを「Alumni Network」と呼び、卒業生とのつながりを維持する文化が広く根付いています。
この「卒業生ネットワーク」の考え方が企業にも波及し、企業を退職した元社員(OB・OG)を「企業の卒業生=アルムナイ」と捉え、つながりを維持する制度が「アルムナイ制度」です。
この制度は2000年代にアメリカの大手企業で先行して導入され、2020年代には日本国内でも注目が高まりつつあります。

1.2 アルムナイ制度の目的と意義
アルムナイ制度は、単なる退職者名簿の作成に留まらず、企業と元社員との「再接続の仕組み」を整えることが目的です。
主な目的は以下のとおりです。
- 再雇用による即戦力確保
- 企業ブランドの維持・向上
- 顧客・パートナーとしての関係維持
- 企業文化の継承
これまで「辞めた人=裏切り者」とする古い企業文化が根強かった日本社会において、アルムナイ制度は「一度退職してもまた戻ってこれる」「円満退職者を尊重する」風土づくりにもつながっています。
1.3 近年の企業におけるアルムナイ制度の注目
近年、人的資本経営の一環として、企業が「人材を資産」として長期的に捉える流れが加速しています。副業解禁や転職の一般化により、終身雇用の時代は終わりを迎えつつあり、一度辞めた人材でもスキルをアップさせて戻ってくることは歓迎されるべきことになりつつあります。
特に大手IT企業や外資系企業では、アルムナイネットワークの形成と活用を戦略的に行っており、中途採用戦略の柱として位置付けている企業も増えています。
2.アルムナイ制度のメリットとデメリット
2.1 企業にとってのアルムナイ制度のメリット
1. 即戦力の再獲得が容易
アルムナイの最大の魅力の一つが、再雇用時の「即戦力性」です。既に企業の組織文化や業務フロー、社内ルールを理解しているため、一般の中途採用者と比べて、オンボーディング期間(職場適応に要する時間)を大幅に短縮できます。
たとえば、あるIT企業では、元社員を再雇用した場合の立ち上がり期間が通常の中途採用より30〜50%短縮されたというデータもあります。特に、プロジェクト進行中の緊急人材補強や、専門的なスキルが必要なポジションでの即戦力確保においては、非常に有効です。
2. ブーメラン社員による文化の強化
一度企業を離れた社員は、外部で異なる企業文化や仕事の進め方を経験します。その結果、自社にいた頃には見えなかった**「自社の強み・弱み」を客観的に捉える視点**を持って戻ってきます。
これは企業にとって極めて貴重な「内と外を知る存在」となり、保守的な組織文化に風穴を開け、イノベーションのきっかけになることも少なくありません。さらに、「また戻ってきたいと思える職場だった」というメッセージは、現役社員のモチベーションや帰属意識の向上にもつながります。
3. 採用コストの削減
通常、中途採用には平均で1人あたり50万〜100万円以上の採用コストがかかるとされています。求人広告、人材紹介会社への手数料、面接対応など、直接的なコストだけでなく、社内リソースの負担も見逃せません。
アルムナイ制度を活用すれば、過去に関係のあった人材へ直接アプローチできるため、これらのコストを大幅に圧縮することが可能です。また、アルムナイが知人を紹介する「リファラル採用」にもつながりやすく、質の高い人材を低コストで確保できる好循環が生まれます。
4. 企業ブランディングの強化
アルムナイ制度は、単なる人事施策にとどまらず、企業のレピュテーション(評判)向上にも貢献します。
円満退職した元社員が自社を「良い職場だった」と他者に伝えることで、企業イメージの向上に寄与します。特にSNSや口コミサイトが影響力を持つ現代において、ネガティブな離職体験よりも、ポジティブな退職エピソードの発信は、将来の求職者に対して大きな説得力を持ちます。
また、「辞めても歓迎される職場」という印象は、現役社員にとっても安心材料となり、離職率の低下や心理的安全性の向上にも寄与します。
2.2 アルムナイ制度のデメリット・リスク
1.既存社員との摩擦
カムバック社員が過去の実績やスキルをもとに、入社直後から高い役職や好待遇を得る場合、社内に軋轢を生むリスクがあります。特に、現場で地道に努力してきた社員からすれば、「一度辞めた人が戻ってきて優遇されるのは不公平」と感じることは自然な反応です。
このような摩擦は、組織の士気低下や信頼関係の崩壊を招きかねません。企業側は、再雇用者の評価や待遇の根拠を透明性高く共有する必要があります。また、既存社員へのフォローアップや説明責任を怠ると、アルムナイ制度が逆に社内分裂の火種になってしまう危険もあります。
2.機密情報の取り扱い
元社員は、在籍時に企業の重要なノウハウや営業情報、顧客データに触れていた可能性があります。こうした情報が、他社での就業中や競合企業への転職時に漏洩するリスクは常に存在します。
また、アルムナイネットワークを通じた再接触時にも、何らかの内部情報が無意識に漏れる可能性があるため、セキュリティ管理や機密保持契約の再締結が不可欠です。
退職後の情報取扱に関するガイドラインやNDA(秘密保持契約)の再確認を徹底することで、リスクを最小限に抑える体制が求められます。
3.制度形骸化の懸念
アルムナイ制度は、適切に設計・運用されなければ形だけの制度になってしまう恐れがあります。名簿を作って終わり、メールを年に1回送って終わり、といった消極的な運用では、アルムナイとの関係性は希薄になり、制度が定着しません。
また、制度導入後に担当者の異動や退職があった場合、後任がその意義や目的を理解していないと、アルムナイとの接点が断たれてしまうケースも珍しくありません。
定期的なイベント、コンテンツ配信、再雇用の事例紹介など、「生きた制度」として機能させる工夫と、中長期的な戦略に基づいた運用体制が不可欠です。
このように、アルムナイ制度には多くのメリットがある一方で、丁寧な設計と運用がなければ、組織に悪影響を及ぼすリスクも伴います。導入にあたっては、単なる一時的施策ではなく、企業全体の人材戦略に組み込む形で活用することが重要です。
2.3 求職者(アルムナイ)側から見たメリットとデメリット
アルムナイ制度の本質的な魅力は、企業だけでなく退職者本人にとっても大きな恩恵がある点にあります。しかし一方で、戻ることに対する不安や心理的障壁も存在します。ここでは、アルムナイ(元社員)が職場に復帰する際のメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します。
【求職者側のメリット】
1. 環境への適応がしやすい
既に在籍経験があるため、組織の文化やルール、業務プロセスをある程度理解しています。新たな環境に一から適応する必要がなく、スムーズに業務に入ることができる安心感があります。
また、旧知の同僚や上司が残っていれば、対人関係の構築も容易であり、入社初期のストレスが大幅に軽減されます。
2. キャリアの中断感を持たずに再開できる
退職後、他社で得たスキルや経験を活かしながら、再び慣れ親しんだ職場でキャリアを継続できるのは大きな利点です。「キャリアの流れが自然に戻る」という意味では、異業種転職よりも心理的負担が小さい場合もあります。
特に「本当は辞めたくなかったけれど、やむを得ず退職した」場合や、「家庭の事情で一時的に離職した」ケースでは、非常に相性の良い選択肢です。
3. 条件の再交渉が可能
再雇用される場合、多くの企業では以前の待遇よりも好条件を提示するケースも存在します。市場価値を客観的に証明できる職歴を携えて戻ることで、交渉の余地が広がり、「以前より納得のいく働き方」が可能になることも少なくありません。
また、勤務地や勤務形態(リモートワークや時短勤務など)についても柔軟に対応してくれる企業が増えてきています。
4. 「出戻り=キャリアの柔軟性」として肯定される時代背景
かつては「一度辞めた会社に戻るなんて恥ずかしい」とされる風潮もありましたが、現代では「転職も、出戻りも自然な選択肢」として認識されつつあります。アルムナイ制度の広がりは、「辞めたら終わり」ではなく、「一時的なキャリアの寄り道」も肯定する文化へと進化しています。
このような社会的な風向きの変化が、求職者側にとっての心理的障壁を取り除く大きな要素となっています。
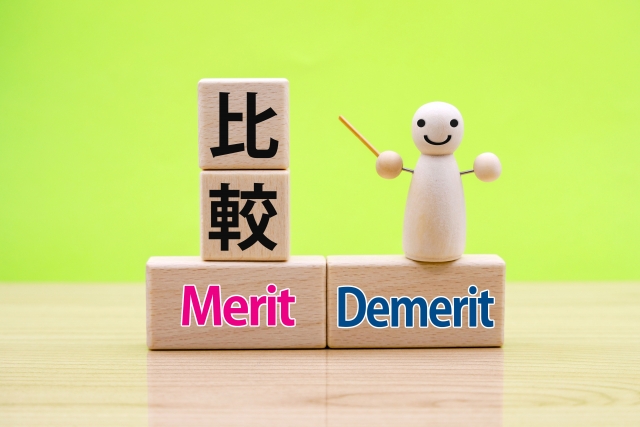
【求職者側のデメリット・リスク】
1. 旧知の人間関係に逆戻りする不安
「以前の上司や同僚との関係がうまくいかなかった」「特定の部署に苦手意識がある」など、退職のきっかけになった人間関係がそのまま残っている場合、復帰後に同じ問題が再燃する可能性があります。
特に組織再編や役職変更がなかった場合、以前と同じ関係性の中で働くことに対する葛藤は少なからず生じるでしょう。
2. 「戻ってきた理由」を問われるプレッシャー
カムバックした社員には、周囲から「なぜ戻ってきたのか」「なぜ辞めたのか」といった疑問が向けられる場面もあります。これは悪意がない場合でも、本人にとってはプレッシャーや気まずさの要因になることがあります。
特に以前と異なる役職や待遇で戻った場合、「昇進を優遇されたのでは」「裏取引があったのでは」といった誤解や嫉妬を受ける可能性もあるため、心の準備と対処力が求められます。
3. 社内文化や制度が変化している可能性
離職から時間が経っている場合、社内制度や組織文化が大きく変わっていることがあります。かつての「勝手知ったる職場」だと思って復帰したのに、実際はカルチャーギャップに戸惑うという事例も珍しくありません。
たとえば、上司や経営方針が変わっていたり、評価制度が刷新されていたりすると、「思っていた職場と違う」と感じ、結果として早期離職につながるケースもあります。
4. キャリア停滞への懸念
中には、「出戻ることで他のチャレンジを放棄したのでは」と自分自身が感じてしまうケースもあります。たとえば、スタートアップや外資系で挑戦をしようと思っていたが、結局慣れ親しんだ企業に戻った──このような選択が、「安定を取ったが成長機会を失った」という自己評価につながることもあるのです。
この場合、再雇用後に「やはり別の選択をすべきだったかもしれない」と後悔するリスクもゼロではありません。
3.アルムナイ制度を導入する企業の実態
3.1 アルムナイ制度の導入企業の事例
- トヨタ自動車
OBとのつながりを重要視し、海外拠点を含めたネットワークを活用中。 - 三井住友信託銀行
アルムナイ対象者にメールニュースや交流会を通じて関係継続。再雇用も積極的に実施。 - パーソルキャリア
アルムナイを「人的資本」として再評価し、社外広報・採用・プロジェクト協業へと展開。 - アクセンチュア・ジャパン
元社員を対象にした「アクセンチュア・アルムナイ・ネットワーク」を運用。再雇用率は高く、戦略的な人材確保に成功。 - サントリーホールディングス
OB・OGとの定期的な交流イベントを実施し、商品アンバサダーや販路拡大の担い手として活用。
3.2 神奈川県におけるアルムナイ制度の動向
神奈川県においても、近年「人材の再活用」と「長期的な関係構築」を目的としたアルムナイ制度の導入が広がりつつあります。特に、横浜市や川崎市といった都市部に加え、湘南・県央・西湘地域など多様な産業構造を持つエリアにおいて、それぞれの事情に即した導入が進んでいます。
特に顕著な傾向として以下のような動きが見られます
- 製造・研究開発型企業での制度活用が活発
技術者・研究職の専門性を再活用する目的で、熟練人材の再雇用ニーズが増加しています。特に厚木・相模原・横須賀などの企業に顕著です。 - 「地域回帰・Uターン型」の再雇用が増加
一度東京に出た人材が地元神奈川に戻るケース、あるいは神奈川から他県へ移動した人材が再び戻ってくる流れがあり、Uターン就職支援とアルムナイ制度がリンクし始めています。 - 横浜市を中心に、スタートアップでも制度導入が進行中
若手の転職率が高いスタートアップ企業でも、「一度離れても関係を切らない」カルチャーが定着しつつあり、カジュアルなアルムナイ制度(SlackグループやLINEオープンチャットなど)を通じた再接続事例が増えています。 - テレワーク普及により、地理的制約を超えた再雇用が現実に
特に湘南・三浦地域など通勤距離のハードルが高いエリアでも、在宅勤務を活用することで、過去の社員を再度リモートワーカーとして迎えるケースが増えています。

3.3 各業界でのアルムナイ制度活用の状況(神奈川版)
◆ IT・情報通信業(横浜・川崎・藤沢エリア)
神奈川県内のIT業界は、東京に本社を持つ大企業のサテライトオフィスや、地場の中小システム開発会社が混在しています。離職率が高い業界特性から、早期からアルムナイ制度導入に前向きな企業も多く見られます。
- 地域IT勉強会やエンジニア同士の横のつながりが強く、アルムナイネットワークを介した再雇用が実現しやすい。
- フリーランスとして独立した元社員を業務委託で再登用するハイブリッド型活用が増加。
◆ 製造業・研究開発職(厚木・相模原・横須賀エリア)
神奈川県は大手自動車メーカーや電子機器メーカーの工場・研究所が点在する技術立県です。退職した技術者・研究職の「即戦力化」が大きな課題となっており、アルムナイ制度の導入効果が極めて高い分野となっています。
- 熟練工・技術職を対象にしたOBネットワークの整備が進行中。
- 定年退職後の再雇用とは異なり、「中堅層で一度離れた人材を呼び戻す」ことが目的となっている。
- 一部企業では、アルムナイ限定の技術研修を設け、スキルアップと復帰支援を同時に行っている。
◆ 医療・福祉・看護業界(横浜市・小田原市など)
神奈川県は高齢化が進む地域であり、医療・福祉分野での人材確保は喫緊の課題です。看護師や介護職員など専門性の高い職種で、出産・育児・介護などで一時離職した人材のカムバック支援がアルムナイ制度と組み合わされています。
- 「復職支援プログラム」や「再教育研修」と連動したアルムナイ制度が病院や福祉施設単位で導入。
- 女性職員の定着・再雇用率向上の一環として、地域行政との連携による制度化も進んでいる。
◆ 金融・保険・不動産業(横浜・川崎エリア)
比較的人脈重視型の業界であり、顧客との関係性や信頼性を重視する傾向が強いため、「元社員の信用力」を活かした再雇用が効果的に機能しています。
- 支店を異動した元社員が、その土地の顧客ネットワークを維持したまま復職する事例も。
- 特に不動産業では、営業・仲介経験者のリターンが増えており、「地域密着型のプロフェッショナル再生産」が狙いとなっています。
3.4 神奈川特有の導入背景と期待
神奈川県では、東京圏に比べて「通勤地の選択肢が広い」「職住近接志向が強い」という地域特性があります。そのため、以下のような導入背景が際立ちます。
- ライフステージに応じたキャリア再設計が可能な地域構造
子育てや介護を経て再就職を考える人材が多く、働きやすい地元企業へのカムバックを希望するケースが増加。 - 多拠点就業・サテライトオフィスとの相性の良さ
湘南・箱根などの観光地勤務を希望する元社員との再接続がテレワークで現実に。 - 地域連携型の人材プール形成が進行中
商工会議所や自治体、地元大学との連携を活かし、「アルムナイ人材バンク」のような仕組みが試行されている地域もあります。
4.アルムナイ採用のプロセスと方法
4.1 記録された退職者との再雇用の方法
アルムナイ制度を活用した再雇用は、通常の中途採用とは異なる特徴があります。特に重要なのは「情報の蓄積と活用」です。企業側は退職者の勤務履歴やスキル、退職理由などを適切に記録・保管し、それをもとに以下のようなプロセスで再雇用を実現します。
- アルムナイデータベースの構築
氏名、部署、スキルセット、退職時の評価、希望勤務地などを記録。 - 定期的な情報提供とコンタクト
メールニュース、ウェビナー、SNSなどで企業の最新動向を伝える。 - 再雇用のタイミングに応じたアプローチ
新規プロジェクト立ち上げ時やポジション空きが生じた際に、即座に候補者として連絡。 - 柔軟な雇用形態の提案
正社員再雇用だけでなく、業務委託・副業・期間契約などの多様な働き方も選択肢に含める。
これらの流れは、単なる「再入社」の枠にとどまらず、アルムナイ一人ひとりのキャリアを尊重する採用活動として機能します。
4.2 カムバック社員と既存社員との関係構築
再雇用されたカムバック社員(ブーメラン社員)は、企業にとって貴重な人材ですが、その受け入れが社内に摩擦を生むこともあります。以下のような対策が重要です。
- 公平な評価制度
再雇用社員と既存社員が同じ基準で評価されることで、不平等感を防ぐ。 - オンボーディングプログラムの強化
カムバック社員向けの再オリエンテーション研修などを通じて、変化した社内体制や文化を再確認してもらう。 - メンター制度の導入
戻ってきた社員に既存社員をメンターとして付けることで、自然な関係構築が促される。 - 心理的安全性の確保
アルムナイ社員が「気を遣われすぎない」「遠慮しすぎない」環境づくりを意識する。
4.3 アルムナイネットワークの活用法
アルムナイ制度の核となるのが、ネットワークの存在です。単なる名簿ではなく、活発に情報と交流が生まれる場であることが理想です。
- 専用SNSやポータルサイトの運営
SlackやFacebookグループ、専用アプリなどを活用して、情報の一元管理と交流促進を図る。 - ニュースレターの配信
企業の近況、プロジェクトの紹介、求人情報などを定期的に発信し、関係性を維持する。 - アルムナイ向けキャリア支援
セミナーや勉強会の開催、キャリアコンサルティングの提供なども有効です。

4.4 アルムナイ制度を成功に導く導入・運用・改善のステップ
企業がアルムナイ制度を導入し、継続的に成果を上げるためには、単なる「仕組み作り」に留まらず、制度の目的設定から運用、評価、改善までの一連のプロセスを丁寧に設計・実行することが求められます。ここでは、導入から運用、評価・改善までを一貫した流れでご紹介します。
ステップ1:制度導入の準備と目的の明確化
アルムナイ制度は、まず企業内の合意形成と、目的の明確化から始まります。
- 目的の定義と共有
- 「退職後も良好な関係を維持したい」
- 「再雇用や業務連携の機会を創出したい」
- 「人材ブランディングや社外アンバサダー育成を狙いたい」
など、企業ごとに異なる目的を明確にし、関係部署と共有します。
- 関係者の巻き込み
- 経営層、法務、人事、広報部門を巻き込むことで、制度の安定性と持続可能性を高めます。
- 制度の対象者を定義
- 例:勤続年数〇年以上、円満退職者に限定、懲戒退職者は対象外 など、ルールの設定も重要です。
ステップ2:制度設計とプラットフォーム構築
制度を形にする段階では、運用設計やコミュニケーションチャネルの整備が求められます。
- 情報管理・プラットフォームの整備
- アルムナイ専用のポータルサイトやSNSグループの作成
- 個人情報保護・退職後の連絡ルールを定める(プライバシーポリシーや同意取得)
- 退職時のフロー整備
- 「アルムナイ制度の案内資料」や「登録申請フォーム」を退職面談などで配布・説明
- 同意を得た上で、連絡先情報やキャリア希望などを収集
- 担当部署・役割の明確化
- アルムナイ対応の専任担当者の設置(人事または広報部門など)
- 定期的な情報更新やフォロー体制の整備
ステップ3:制度の運用と継続的コミュニケーション
導入後の肝は「活用」ではなく「関係性の継続」です。アルムナイとの接点を維持・深化させる運用が重要になります。
- 定期的な情報発信と接点づくり
- ニュースレター、近況アンケート、OB/OG会の開催
- 誕生日の『おめでとうメール』
- 新規プロジェクトへの協力依頼、イベント招待など
- アルムナイを巻き込む仕組み
- 社内のメンターや講演会講師として招く
- 人材紹介・リファラル採用を通じたネットワーク活用
- 地元の夏祭りやイベント・交流会などの参画の際に応援を依頼する
- 社内とアルムナイのつなぎ役を育成
- 現役社員とアルムナイの関係をサポートする「コミュニティマネージャー」的な役割の導入
ステップ4:効果測定と制度の改善
アルムナイ制度は作って終わりではなく、「育てていく制度」です。導入後の成果や課題を定期的に見直し、ブラッシュアップしていくことが成功の鍵です。
- KPIの設定と効果測定
- アルムナイ再雇用者数
- リファラル経由の採用人数
- OB/OGイベントの参加率
- 社内の離職率の変化 など
- アルムナイからのフィードバック活用
- 年1回のアンケートや個別ヒアリングを通じて、制度に対する声を収集
- 寄せられた意見をもとに改善策を立案
- 制度の柔軟な進化
- 対象者の拡大(例:派遣社員や契約社員も対象に)
- オンライン施策の強化(例:バーチャルOB会、キャリアセミナー)
- 新卒採用の内定式などで社員インタビューなど役割を持たせる

5.アルムナイ制度導入のステップ
5.1 初期の計画と組織内周知の方法
- 目的の明確化
単なる人材確保に留まらず、企業ブランディングや人的資本活用との連動を明示する。 - 対象範囲の設定
退職後何年までを対象にするか、希望者のみか、全退職者を対象にするかを検討。 - 社内啓発活動
現役社員への説明会、イントラネットでの告知、マネージャー層の理解促進が重要。
5.2 必要な規定と条件の整備
- 個人情報の管理方針
- 再雇用条件(処遇・等級など)
- 社外活動時の情報共有の範囲
など、法的な観点も含めた制度設計が必要です。特に情報保護に関する法令(例:個人情報保護法)への準拠は必須となります。
5.3 評価と改善のためのデータ収集
- アルムナイ登録率の推移
- 再雇用までの平均期間
- 復帰後の定着率・満足度
これらのデータを蓄積・分析し、PDCAを回していくことが制度の長寿命化に直結します。
6.アルムナイ制度の未来と展望
6.1 企業文化と働き方の変化に伴うアルムナイ制度の進化
- ジョブ型雇用の拡大
終身雇用からジョブ型へと移行する中で、「会社を一度辞めても、再び仕事ベースで戻る」選択肢が広がる。 - 副業・複業との親和性
アルムナイが「社外協業パートナー」として企業と関わるハイブリッドな関係性が構築されていくでしょう。
6.2 コスト削減とエンゲージメント向上に向けた取り組み
採用にかかるコストは年々増加傾向にありますが、アルムナイ制度はその抑制手段となり得ます。同時に、アルムナイとの良好な関係性を維持することで、企業ブランドの維持や社員エンゲージメントの向上にも貢献します。
6.3 生産性と社員モチベーション向上の可能性
「辞めてもまた戻れる職場」という安心感は、現役社員の心理的安全性を高め、過度な退職への恐れや不安を軽減します。これが、結果的に社員の主体的な働き方や生産性向上につながるという効果も見逃せません。
7.最後に
総括:アルムナイ制度は「企業と個人の双方に利益がある制度」
アルムナイ制度を通じて職場に戻るという選択は、企業にとっても、求職者個人にとっても高い相互利益をもたらします。しかし、ただ「戻れる」ことだけが目的になってしまうと、両者にとってマイナスに作用する場合もあります。
そのため、復帰前には以下の点を整理しておくことが大切です。
- 自分がなぜ辞めたのか? なぜ戻りたいと感じているのか?
- 以前の職場環境と現在の期待にギャップはないか?
- 再雇用後、自分はどのような価値を提供できるか?
企業と個人、双方が「選び直す」関係としてアルムナイ制度を活用することで、よりしなやかで強固な人材戦略とキャリア形成が可能になります。
アルムナイ制度は、単なる「辞めた社員の連絡帳」ではなく、企業と人材の新しい関係性を築くための強力なツールです。
一度辞めた社員が、他社で経験を積んで戻ってくる
──そこには「育てた企業」と「育てられた人材」の相互尊重があります。
企業にとっては採用・教育コストを抑えつつ即戦力を確保できる大きなメリットがあり、社員にとっても「キャリアを一貫して支えてくれる場」があるという安心感につながります。
また、アルムナイ制度を導入することで、退職という行為をネガティブなものではなく、「キャリアの一時的な別ルート」として前向きに捉える風土が醸成されます。このように考えると社内でキャリアを作るのも1つのルートですが、社外に出てキャリアを作るのも別ルートとして捉えることもできます。
株式会社S.I.Dはあなたのキャリア形成のサポートが出来たらと考えています。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
―――人生100年時代。
働き方もキャリアも複線化し、多様化する中で、
アルムナイ制度は今後ますます企業活動における重要な仕組みとなっていくでしょう。