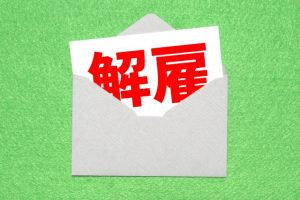目次
1.退職代行を利用するメリットとデメリット
2.退職代行が台頭してきている背景とは
3.退職代行の実績とトラブル事例
4.退職代行で働いている人ってどんな人?
5.退職代行における個人情報と守秘義務
6.ブラックリストとは?実際にあるの?
7.最後に・・・
1.退職代行を利用するメリットとデメリット
1.1 退職代行の基本とは?
退職代行とは、労働者が自身で退職の意思を伝えづらい場合に、第三者が代わりに雇用先へ退職の意向を伝えてくれるサービスです。一般的には、退職届の提出、上司への連絡、必要な書類の送付などを代行します。法律上、本人の意思による退職は認められているため、第三者が代行して伝えることも問題ありません。
1.2 退職代行を依頼するメリット
- 精神的な負担の軽減
職場に行くのが苦痛、上司との対面が怖い、ハラスメントを受けているなどの状況で、精神的な安堵が得られます。 - 即日退職が可能
サービスによっては当日中に退職の連絡をしてくれ、その日から出社不要となる場合もあります。 - 法的知識のある担当者が対応
弁護士が運営する退職代行なら、未払い残業代の請求なども相談可能です。 - 煩雑な手続きを一任できる
退職届や私物の返却など、退職時に必要な作業を代わりに行ってくれます。
1.3 退職代行のデメリットと注意点
- サービスによって対応範囲が異なる
非弁行為(法律業務)を行えない業者では、会社との交渉や金銭請求はできません。 - 費用が発生する
平均して2~5万円程度の費用がかかります。弁護士事務所の場合はさらに高額になることも。 - 会社側とのトラブルリスク
感情的なもつれや業務の引継ぎがうまくいかないなどの問題が起こる可能性があります。 - 将来の職場への印象懸念
履歴書への記載は不要ですが、次の職場で退職理由を聞かれた際に対応が必要です。
2.退職代行が台頭してきている背景とは

近年、特に20〜30代の若年層を中心に、「退職の意志を自分で伝えることができない」「上司と直接話すのが怖い」といった理由で退職代行を利用するケースが急増しています。この背景には、単なる“甘え”ではなく、職場における心理的安全性の欠如や、世代間で異なる価値観、そして職場文化の変化が深く関係しています。
2.1 心理的ハードルが極めて高い現実
- 「退職の話を切り出したら怒鳴られそうで怖い」
- 「辞めたい理由をうまく説明できず、詰められるかも…」
- 「直属の上司が感情的で、報復的な対応をされそう」
こうした声は、Z世代やミレニアル世代に限らず、幅広い層から聞かれるようになっています。特に心理的安全性が担保されていない職場では、退職を申し出ること自体が大きなリスクと感じられます。
心理的安全性とは、「自分の意見を安心して言える」「失敗や異議を表明しても非難されない」職場の雰囲気を指しますが、これが欠けている環境では、退職の意思表明=攻撃対象になる行為と捉えられることすらあります。
そのため、退職を申し出るどころか、「話しかける」「相談する」といった基本的なコミュニケーションさえ困難になるケースも存在します。
2.2 Z世代・ミレニアル世代の価値観と職場観の変化
Z世代(1996年以降生まれ)やミレニアル世代(1981~1995年生まれ)は、従来の「我慢して働く」「上司の顔色をうかがう」ことを美徳とする価値観よりも、心の健やかさと働きやすさを大切にする傾向があります。
- 無理に上下関係を維持するより、自己のメンタルヘルスを優先
- 「察する文化」よりも、対話・共感をベースにした関係性を重視
- 会社を「人生を捧げる場所」ではなく、「自分の人生を充実させる手段」として捉える
そのため、指導という名の叱責や、暗黙の同調圧力、過度な責任の押し付けといった旧来型のマネジメントには強いストレスを感じやすくなっています。
特に、心理的安全性が低い職場では、自分の意思を尊重してもらえる可能性が少ないと感じ、退職を伝えること自体が「反逆行為」のように受け止められると懸念する人が多くなります。

2.3 SNS・メディアの影響で認知度が上昇
- 「EXIT」などの先駆者的なサービスがメディア露出し、話題に。
- YouTubeやTikTok、X(旧Twitter)などで体験談が拡散。
- 「気軽に使える」「退職=もっと自由にできること」という印象が広まっている。
2.4 法律上、退職は「自由」であることが知られてきた
- 日本の労働法では、「退職は労働者の権利」と明確に定められている。
- 法的知識の普及により、「辞めたくても辞められない」という思い込みが崩れてきている。
- 特に弁護士が運営する退職代行が増えたことで、安心感もアップ。
2.5 すぐに辞められる「即日対応」ニーズにマッチ
- 「もう明日から出社したくない!」という即時的な感情に応えられるのが退職代行。
- スマホ1つで完了する簡便さも、忙しい現代人に支持されている。
- 特に精神的・肉体的に追い詰められている人には、**“最終手段ではなく最善の選択”**になっている。
2.6 「辞めたあとのサポート」も充実してきた
- 転職エージェントと提携して、次の職場探しも支援するサービスが登場。
- 精神ケアや法的相談、未払い請求などのアフターケアが手厚くなっている。
2.7 退職代行は「逃げ」ではなく、「自分を守る手段」
退職代行の利用は、決して「コミュニケーション能力がない」ことの表れではありません。むしろ、自身の心の健康と将来のキャリアを守るための理性的な行動であると捉えるべきです。
特に若年層にとって、「退職を切り出す」という行為は、単なる事務的手続きではなく、職場での人間関係や評価、自己価値観にまで影響を与える大きなハードルです。その壁を乗り越えるための一手段として、退職代行というサービスが存在することは、これからの多様な働き方を支えるためにも必要不可欠なのです。
| 時代背景 | 退職代行が応えるニーズ |
| 人間関係に悩む若者の増加 | 直接対面を避けた円満退職 |
| ハラスメントやブラック労働 | 自己防衛としての退職支援 |
| SNSによる共感・拡散 | 使いやすさ・心理的ハードルの低下 |
| 法律知識の普及 | 労働者の権利としての「退職」認識 |
| 即日退職のニーズ | スピーディな行動が可能な時代 |
3.退職代行の実績とトラブル事例
3.1 退職代行サービスの信頼性
退職代行は2018年頃から注目され始め、現在では多数のサービスが存在します。実績としては、年間1万件以上の退職をサポートしている大手業者もあり、社会的にも一定の認知を得ています。
3.2 実際にあったトラブル事例
- 引継ぎ問題による業務混乱
退職連絡のみで引継ぎが不十分だったため、後任者に大きな負担がかかったケース。 - 未払い給与の請求漏れ
法的知識のない代行業者に依頼し、未払い賃金を回収できなかった例。 - 違法業務の実施
非弁業者が会社と交渉し、弁護士法違反とされた事例。 - 有給休暇の消化を拒否された
有給消化を希望していたが、会社が拒否し、適切な主張ができずに消化できなかった事例。 - 社宅退去トラブル
退職に伴い社宅を退去する必要があったが、急な退去要求や原状回復をめぐってトラブルとなったケース。
■ トラブルを回避するためのポイント
- 弁護士が運営するサービスを選ぶ
- 実績・口コミの確認
- 契約内容の事前確認(対応範囲・料金・返金規定など)
3.3 退職代行の流れとステップ
■ 依頼から完了までの流れ
- 無料相談・問い合わせ
- 契約手続き・料金支払い
- 退職意思の確認とヒアリング
- 退職代行の実施(会社への連絡)
- 退職届の提出・私物回収・貸与品返却
- 退職完了・証明書の取得
■ 退職代行サービスの選び方
- 弁護士対応かどうかの確認
- 料金の明確性とサポート範囲
- 口コミや評判の良さ
- アフターケアの有無(転職支援・法的相談など)
■ 必要な書類と準備
- 退職届の作成(代筆も可能)
- 健康保険証・社員証などの返却準備
- 源泉徴収票・離職票の受け取り確認
3.4 弁護士を利用する利点
■ 退職代行と弁護士の違い
退職代行は基本的に「伝えるだけ」の業務。一方で、弁護士は労働法に基づき、残業代請求やハラスメント対応などの交渉が可能です。
■ 弁護士に依頼すべきケース
- 未払い賃金・残業代がある
- パワハラ・セクハラなどの証拠がある
- 退職を妨害されている
- 退職後に訴訟を検討している
■ 弁護士費用の相場と実績
- 退職代行費用:3~10万円程度
- 残業代請求の成功報酬:回収額の20~30%
- 無料相談から始められる事務所も多数:実績としては、残業代300万円の回収に成功した事例や、ハラスメント証拠を基に慰謝料を得た例もあります。
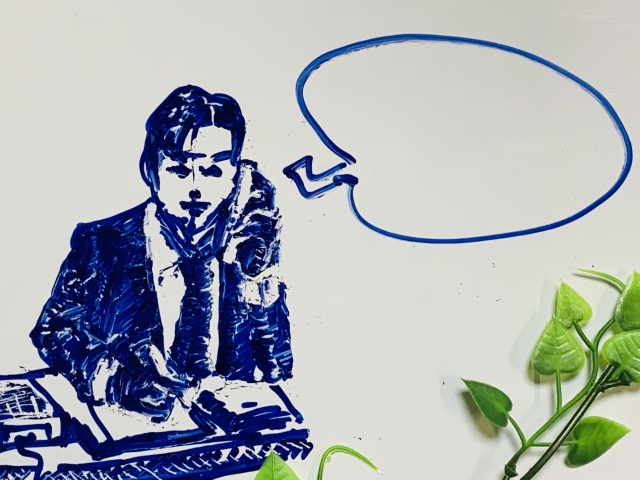
3.5 退職代行を利用した後の選択肢
■ 転職へのステップ
退職代行後は転職活動に専念できます。転職エージェントの利用や自己分析によるキャリア再設計が大切です。
■ 退職後の心構えと注意点
- 自責感を持たないこと:退職は正当な権利です。
- 心身のケアを大切に:ストレスやうつ症状がある場合は専門医へ。
- 職歴整理とキャリア棚卸し:「キャリアの棚卸し」を行い自身の強みを把握しましょう。
▶「キャリアの棚卸し」の記事はコチラ
▶「職務機歴書の作り方」の記事はコチラ
■ 未払い賃金の請求方法
- 内容証明郵便で請求
- 労働基準監督署への申告
- 弁護士による交渉・訴訟提起
3.6 退職代行に対する誤解と真実
■ 心配される失敗談
- 「会社から連絡が来たらどうしよう…」→ ほとんどの代行は連絡遮断まで対応。
- 「ブラックリストに載るのでは…」→ そのようなリストは存在しません。
■ 有名な退職代行サービスの評判
■ サービスの選択のコツ
- 自分の状況にあったサービスを選ぶ(法的対応が必要かどうか)
- 即日対応や深夜対応の有無
- 料金体系が明確であること
3.7 退職代行に関するよくある質問
■ 退職代行の利用は本当に安全か?
法的に退職は労働者の自由であり、代行がその意思を伝えることは違法ではありません。
信頼できる業者を選ぶことで、安全に退職できます。
■ 退職代行サービスの料金相場は?
- 一般的代行:2~5万円
- 弁護士代行:3~10万円
- 成功報酬型もあり、事前に確認が必要です。
■ 退職代行を依頼する際の注意点のまとめ
- 弁護士かどうかを確認する
- 契約内容を事前に熟読する
- 退職後の生活設計も忘れずに
■ 弁護士と退職代行会社の比較表
| 項目 | 弁護士による退職代行 | 一般的な退職代行会社 |
| 料金相場 | 3〜10万円+成功報酬(交渉案件含む) | 2〜5万円(固定料金) |
| 法的交渉 | 可能(未払い残業代・慰謝料請求など) | 不可(非弁行為に該当) |
| 会社との直接交渉 | 可能(退職妨害への対応も含む) | 不可(伝達のみ) |
| 即日対応 | 可能だが要相談(事務所の対応次第) | ほとんどが即日対応可能 |
| 安心感・信頼性 | 高い(国家資格者の対応) | 業者によって差がある |
| 対応の柔軟性 | 高い(状況に応じた法的対応) | 限定的(マニュアル対応中心) |
| 成功報酬の発生 | 回収額の20〜30%程度(別途) | なし(基本的に定額) |
| 主な利用ケース | トラブルを抱えている/退職妨害されている場合 | 精神的な負担軽減が目的の場合 |
4.退職代行で働いている人ってどんな人?
退職代行の仕事は、単なる「伝言係」ではなく、依頼者の人生に深く関わる繊細で責任のある職業です。そこで働く人々には、以下のような背景や想いを持つ人が多くいます。
■ 元人事や労務経験者
大手企業や人材系会社での人事・労務経験があるスタッフが多く、退職に関わる実務知識や、企業とのやり取りのノウハウを持っています。相手企業との連絡も、落ち着いた対応が可能です。
■ カウンセリングマインドを持つ人
精神的に追い詰められている依頼者と接する場面も多いため、心理カウンセリングの知識や、共感力を大切にする人が活躍しています。中には産業カウンセラーの資格を持つスタッフも。
■ 法律知識のある専門職(弁護士含む)
弁護士事務所で提供されている退職代行では、当然ながら労働法に精通した弁護士やパラリーガル(法律事務職)が対応します。依頼者の法的保護を第一に考え、訴訟も視野に入れた戦略を立てます。
■ 自身が退職で苦しんだ経験を持つ人
過去に「退職できずに苦しんだ」当事者経験を持つ人も多く、その経験がモチベーションになってこの仕事に就いたという例も珍しくありません。依頼者に寄り添う姿勢が強いのが特徴です。
有名退職代行サービスの比較:EXIT vs 弁護士法人みやび
| 項目 | EXIT | 弁護士法人みやび |
| 運営形態 | 民間企業(株式会社) | 弁護士法人 |
| 料金(税込) | 一律 20,000円(正社員) 10,000円(アルバイト) | 着手金:55,000円〜 ※別途、成功報酬あり(賃金請求等) |
| 法的交渉の可否 | 不可(交渉や請求は対応外) | 可(未払い賃金・損害賠償請求・慰謝料請求など) |
| 即日対応 | 可能(当日朝でも受付可) | 可能(状況により要相談) |
| 連絡対応の範囲 | 会社への退職連絡、書類の受け渡し依頼など | 上記に加え、会社との法的交渉が可能 |
| 利用実績 | 年間7,000件以上(公式発表) | 退職代行だけでなく、労働問題の解決実績多数 |
| サポート体制 | LINEやメールでの相談・進捗連絡 | 電話・メール相談、法律相談も対応可 |
| おすすめの人 | 手軽にすぐ辞めたい人 法的トラブルがない人 | ハラスメント・未払い・退職妨害など問題を抱えている人 |
5.退職代行における個人情報と守秘義務
5.1 個人情報の取り扱いについて
退職代行サービスでは、以下のような個人情報を取り扱うことが一般的です。
- 氏名・生年月日・住所
- 勤務先の会社名や部署
- 退職理由や現在の勤務状況
- 給与・就業条件・ハラスメント等の労働環境情報
これらの情報は、退職手続きのために必要最小限の範囲で使用されます。
ほとんどの業者は、個人情報保護法に則ったプライバシーポリシーを策定しており、情報の第三者提供は原則として行われません。利用前には、各サービスの「プライバシーポリシー」や「利用規約」を必ず確認しましょう。
5.2 守秘義務の有無
- 弁護士が対応する退職代行サービス(例:弁護士法人みやびなど)には、法律上の守秘義務があります。
→ 顧客の相談内容や提供された情報を外部に漏らすことは、法律(弁護士法第23条)で禁じられています。 - 民間の退職代行業者の場合、守秘義務は「業務上のモラル」や「契約内容」に依存します。
→ 契約書や利用規約に「秘密保持に関する条項」があるかどうか確認が必要です。
トラブルを防ぐためのチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
| ✅ プライバシーポリシーの有無 | 個人情報の管理方針が明記されているか |
| ✅ 守秘義務に関する記載 | 契約書や規約に「秘密保持」の文言があるか |
| ✅ 情報の第三者提供について | 情報提供の同意なしに第三者へ渡さない旨があるか |
| ✅ 実績や評判の確認 | 情報漏洩のトラブル事例がないか、SNSや口コミで確認 |
6. ブラックリストとは?実際にあるの?
▶ 一般的に「ブラックリスト」というものは存在しない
労働者が退職代行を使ったことによって、企業間で共有される「ブラックリスト」のような公式なリストは存在しません。
転職市場では、個人情報の扱いが厳格に管理されており、企業が「この人は過去に退職代行を使った」といった情報を入手することはまずできません。
▶ 個人情報保護法により制限あり
企業が第三者に従業員の退職理由や利用サービスを漏らすことは、個人情報保護法違反となるため、法的にも情報共有はできません。
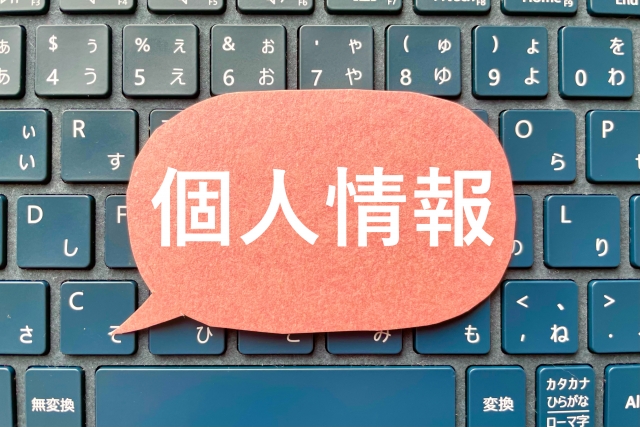
■ なぜ「ブラックリスト」への不安が広まるのか?
- SNSや掲示板で「退職代行使ったら次の会社にバレた」といった体験談がある
- 会社の上司が「ブラックリストに載るぞ」と脅してくるケース
- 業界内の狭いつながりを気にする(例:医療業界やIT業界の一部など)
➡ ただし、これらは噂や一部の特殊な例に過ぎず、原則として退職代行利用の履歴が外部に漏れることはありません。
■ 転職活動への影響はある?
▶ 基本的に影響なし
履歴書や職務経歴書には、「退職代行を使ったかどうか」を記載する義務はありませんし、面接で聞かれることもまずありません。
▶ ただし、退職理由の説明は必要
退職代行の利用とは関係なく、前職の退職理由については面接で聞かれることがあります。
このときは、「ハラスメントがあった」「職場の環境が合わなかった」など、前向きに言い換える工夫をして伝えましょう。
■ ブラックリストに載る心配は不要!
| 不安要素 | 実際のところ |
| ブラックリストの存在 | ❌ 存在しない |
| 転職先にバレる可能性 | ❌ 基本的にバレない |
| 法的リスク | ❌ なし(退職の自由は労働者の権利) |
| 会社が脅してくる | ⚠️ 事実でも違法な脅迫行為になる可能性あり |
■ ワンポイントアドバイス
退職代行を使ったとしても、自分の人生をよりよくするための選択であり、後ろめたさを感じる必要はありません。堂々と、自分のキャリアを築いていきましょう。
7.最後に・・・
退職代行の利用は、単なる「逃げ」ではなく、自分自身の人生と未来に対する真剣な選択です。職場環境や人間関係、心身の不調によって退職の決断が困難になっている現代において、退職代行は「一歩踏み出すための手段」として大きな意味を持ちます。
もちろん、すべての問題が一瞬で解決するわけではありません。退職後の手続きや転職活動、心のケアなど、乗り越えるべきステップは残ります。しかし、自分の意思で「終わらせる」経験は、次の挑戦への確かな原動力となるはずです。
退職はゴールではなく、新たなスタート。だからこそ、苦しみや不安の中で立ち止まっているあなたに伝えたいのは、「無理に一人で抱え込まなくてもいい」ということです。
信頼できる退職代行サービスや弁護士を味方につけ、あなた自身の人生を、あなたの手に取り戻してください。
それでも不安な時には私達、株式会社S.I.Dの転職サポートを受けているのも1つです。
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
これまでの努力は、決して無駄にはなりません。
これから始まる新しいステージに向けて、前を向いて歩き出しましょう。