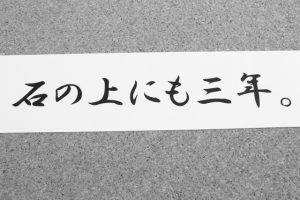目次
1.アイビーの面談技法とは
2.アイビーのかかわり行動の4要素
3.「5段階の面接構造」の理解
4.マイクロカウンセリングの実践
5.信頼関係の構築のために必要な技法
6.最後に・・・・
1.アイビーの面談技法とは

1.1 アイビーの視点から見るカウンセリングの重要性
転職活動において、「自分をどう理解し、どう伝えるか」は成功の鍵を握ります。
そのために役立つのが、カウンセリング心理学の基礎理論として知られる「アイビー(Allen E. Ivey)」の面談技法です。
アイビーはアメリカの心理学者であり、教育・心理・キャリア支援の分野において“マイクロカウンセリング”の体系化を行った人物として知られています。
彼の理論は、単なる心理カウンセリングに留まらず、キャリア面談やコーチング、転職相談など「人と人が深く関わるあらゆる場面」に応用可能です。
特に転職エージェントやキャリアアドバイザーの面談でこの技法が活用されており、クライエント(求職者)との信頼関係構築に欠かせないスキルとして知られています。
1.2 信頼関係構築に必要な心理学的背景
信頼関係(ラポール)の構築は、カウンセリングの基盤です。
アイビーは、「人は理解されたと感じたときに初めて変化する」と述べています。
この考え方は、転職面談においても同じです。
たとえば、求職者が「なぜ転職したいのか」を話すとき、
アドバイザーがすぐにアドバイスをせず、
「そう感じたのですね」、「その経験は大きな意味がありましたね」と受け止めることで、クライエントは「理解してもらえた」と感じます。
この“理解の共有”こそが、信頼を生む第一歩です。
心理学的には、ロジャーズの来談者中心療法が背景にあります。
ロジャーズはカウンセリングの基本的条件として、
- 受容 (Unconditional Positive Regard)
- 共感的理解(Empathic Understanding)
- 自己一致 (Congruence)
を挙げています。
アイビーはこれらをさらに実践的なスキルとして体系化し、「マイクロカウンセリング」として整理しました。
1.3 マイクロカウンセリングの基本とその効果
マイクロカウンセリングとは、カウンセリングで使われる複雑な技法を「誰でも学び、使えるように細分化したスキル群」です。
例えば、
- 傾聴
- 要約
- 質問
- 感情の反映
- フィードバック
など、一つひとつの技法を段階的に学ぶことができます。
転職活動におけるキャリア面談でも、アドバイザーがこの技法を使うことで、
- 求職者が安心して本音を話せる
- 価値観や希望を正確に把握できる
- 面談後の行動変容を促せる
という効果が期待できます。
つまり、アイビーの理論は「人を動かすコミュニケーションの科学」なのです。
2.アイビーのかかわり行動の4要素

2.1 かかわり行動の定義と重要性
アイビーは面談における「関わり方(かかわり行動)」を次の4要素に分類しました。
- 視線(Eye Contact)
- 表情(Facial Expression)
- 姿勢(Body Posture)
- 言語的・非言語的反応(Verbal/Non-Verbal Behavior)
この4つが適切に機能することで、クライエントは「安心感」「信頼感」を抱き、より深い自己開示を行うようになります。
例えば、キャリア面談で「前職を辞めた理由」を話す場面。
アドバイザーが軽くうなずき、穏やかな表情で「そうでしたか」と相づちを打つだけでも、クライエントの語りは深まります。
2.2 4要素を活用した効果的な質問技法
かかわり行動を踏まえたうえで、質問を行うことが大切です。
質問には大きく分けて2種類あります。
- 開かれた質問(Open Question):「どのように感じましたか?」「なぜそう思ったのですか?」
- 閉じた質問(Closed Question):「はい」「いいえ」で答えられる質問。
面談の初期段階では、開かれた質問を中心に、相手の考えを自由に引き出すことがポイントです。
例:
「前職でやりがいを感じた瞬間はどんなときでしたか?」
「転職を考え始めたきっかけを教えていただけますか?」
こうした質問は、クライエントの“内面の言葉”を引き出し、信頼関係の形成を促進します。
2.3 感情の反映とその実践的応用
感情の反映とは、クライエントの言葉の背後にある「気持ち」を読み取り、それを言葉で返す技法です。
たとえば、クライエントが「前の職場では上司と合わなかった」と話したとき、
アドバイザーが「上司との関係でストレスを感じていたのですね」と返すことで、クライエントは「自分の感情を理解してもらえた」と感じます。
転職支援では、この技法が特に重要です。
なぜなら、多くの求職者は“ネガティブな経験”を抱えたまま来談するからです。
感情の反映を通じて、過去を整理し、次に向かうエネルギーを取り戻す支援ができます。
3.「5段階の面接構造」の理解

3.1 面接構造の全体像とその意義
アイビーは、効果的な面接を「5つの段階」に整理しました。
これは転職面談にも応用可能なフレームワークです。
- リレーションの形成(関係構築)
- 問題の明確化
- 目標設定
- 解決策の検討
- 行動の促進と終結
この5段階を意識することで、面談全体を整理しやすく、相手の理解と行動変化をスムーズに導けます。
各段階でのクライエント観察技法の役割
アイビーの理論では、「観察技法」が非常に重要です。
言葉だけでなく、相手の表情・声のトーン・姿勢・沈黙など、非言語的な情報から感情を読み取るスキルが求められます。
たとえば、クライエントが「今の仕事に不満はない」と言いながらも、
目線をそらし、声が沈んでいた場合、
本心では「迷い」や「不安」を抱えている可能性があります。
こうした“非言語のサイン”を見逃さないことが、信頼関係構築の土台です。
3.2 面接での焦点の当て方と具体例
面談の中で「どこに焦点を当てるか」は非常に重要です。
焦点を誤ると、問題が深掘りできず、表面的なアドバイスで終わってしまいます。
焦点を当てるべきポイントには次の3つがあります。
- 行動 :何をしているか(例:転職サイトを見ている、応募をためらっている)
- 感情 :どう感じているか(例:焦り、不安、期待)
- 意味づけ:その行動や感情にどんな意味を持たせているか
たとえば、求職者が「転職活動がうまくいかなくて落ち込む」と話した場合、
単に「頑張りましょう」ではなく、
「うまくいかないときにどんな気持ちになりますか?」と感情に焦点を当てることで、
本人の“価値観”や“自己認識”を引き出せます。
4.マイクロカウンセリングの実践

4.1 マイクロカウンセリングとは何か
マイクロカウンセリングは、カウンセリング技法を「誰でも練習・実践できる小単位のスキル」として体系化したものです。
アイビーは、面談を単なる“感情の共感”に留めず、「行動変化を促すための構造化されたプロセス」として整理しました。
この考え方は、キャリア面談や転職支援において非常に実践的です。
多くの転職者は、「自分が何をしたいのか分からない」、「今のままでいいのか不安」といった“漠然とした悩み”を抱えています。
そのため、感情面の共感だけではなく、行動を明確に導く面談スキルが必要です。
マイクロカウンセリングでは、
- クライエント(求職者)の話を積極的傾聴によって引き出し
- 感情や価値観を整理し
- 最後に行動目標を設定する
という流れを重視します。
つまり、単なる“相談”ではなく、「自己理解と行動変容を結びつける支援」なのです。
4.2 行動と感情に基づいたカウンセリング技法
アイビーは、「言葉(Cognition)」と「感情(Emotion)」と「行動(Behavior)」の3つの側面が、クライエントの変化を生み出す鍵だと考えました。
これを**CEBモデル(Cognition, Emotion, Behavior)**と呼びます。
たとえば、求職者が「面接で緊張して上手く話せない」と言った場合、
- 認知(Cognition):自分は緊張しやすい、失敗したら評価が下がる
- 感情(Emotion):不安、恐れ、焦り
- 行動(Behavior):声が小さくなる、目線が下がる
といった構造が見えます。
マイクロカウンセリングでは、これらの要素を1つずつ整理し、本人が“気づき”を得られるよう導きます。
例:
「緊張してしまうということですが、どんな場面で特に強く感じますか?」
「その時、体や表情にどんな変化がありましたか?」
こうした質問を重ねることで、クライエントは「自分の反応パターン」を認識し、コントロールする手がかりを得ます。
キャリア支援においても、この“気づきの促進”が行動変化への第一歩です。
4.3 ヘルピーなカウンセリングを実現する方法
「ヘルピー(Helpee)」とは、支援を受ける側、つまりクライエントのことです。
マイクロカウンセリングでは、アドバイザー(ヘルパー)が主導するのではなく、ヘルピーの内面の力を引き出すことを目的としています。
転職面談に置き換えると、アドバイザーが一方的に“求人紹介”をするのではなく、
クライエントが「自分の希望」「価値観」「譲れない条件」に気づけるよう支援することです。
たとえば、
- 「今の職場で満たされていないのはどんな点ですか?」
- 「これまでで一番やりがいを感じた瞬間はいつですか?」
といった質問を通じて、本人の“軸”を明らかにしていきます。
ヘルピー中心の支援が行えるアドバイザーほど、面談後に「話してよかった」「方向性が見えた」という反応を得やすくなります。
その根底には、アイビーの“共感的・構造的アプローチ”があるのです。
5.信頼関係の構築のために必要な技法

5.1 クライエントとの信頼関係を深める手法
信頼関係(ラポール)の構築は、面談の成否を左右します。
転職相談の現場では、初回面談でどれだけ「この人になら話しても大丈夫」と思ってもらえるかが重要です。
アイビーは、信頼構築のために以下のステップを推奨しています。
- 受容的態度:評価せず、ありのまま受け止める
- 共感的理解:相手の感情を汲み取り、言葉にする
- 真摯な姿勢:誠実さ、一貫性、率直さを持つ
特に転職面談では、「前職の退職理由」「キャリアの停滞」「家族や年齢に関する不安」など、デリケートな話題が多く出ます。
ここで“否定的な反応”や“早すぎる助言”をしてしまうと、クライエントは心を閉ざしてしまいます。
信頼は、共感からしか生まれません。
相手を変えようとする前に、まず「理解しようとする姿勢」を持つこと。
これがアイビー理論の核心です。
5.2 カウンセリングにおける言語的および非言語的アプローチ
カウンセリングでは、言葉よりも「非言語的表現」が重要な意味を持ちます。
心理学者のメラビアンによる研究では、コミュニケーションの印象形成において、
- 言語情報:7%
- 声のトーン:38%
- 視線・表情・姿勢などの非言語情報:55%
が影響するとされています。
つまり、どんなに良い言葉を使っても、表情や姿勢が伴わなければ、信頼関係は築けません。
たとえば、転職面談中にアドバイザーがPCばかり見ていたらどうでしょうか?
どんなに「あなたのキャリアを大切にしています」と言っても、態度が矛盾しているため、相手は信頼しません。
逆に、相手の話を聞くときに体を前傾し、うなずきながら視線を合わせるだけで、「この人は本気で話を聞いてくれている」と伝わります。
非言語コミュニケーションは、言葉よりも雄弁に“信頼”を語るのです。
5.3 相手の目標に寄り添うための必要なスキル
キャリア面談の目的は、単に“仕事を紹介すること”ではなく、クライエントが「自分の人生の方向性を見出すこと」です。
そのためには、アドバイザーが“相手の目標”に心から寄り添うスキルが求められます。
その代表的なスキルが、以下の3つです。
- リフレーミング(Reframing)
→ ネガティブな経験を新たな意味で捉え直す。
例:「失敗」=「学びを得た経験」。 - サマライジング(Summarizing:要約)
→ クライエントの発言を整理し、本人に返す。
例:「つまり、今の仕事では成長実感が得られていないのですね。」 - フィードバック(Feedback)
→ クライエントの気づきを促すコメント。
例:「今の話を聞いていると、“責任を持って任されたい”という思いが強いように感じます。」
これらのスキルは、相手を導くのではなく、“共に気づく”ための技法です。
結果として、クライエントは「自分の中に答えがあった」と実感し、面談をポジティブな経験として受け止められます。
6.最後に・・・・
アイビーの面談技法は、単なる心理学理論ではありません。
それは、“人と人とが本当の意味で理解し合うための対話の技術”です。
転職活動においても、この考え方は極めて重要です。
なぜなら、転職とは「自分を見つめ直し、未来を選び取る」行為だからです。
カウンセリング的な面談を通じて、
- 自分が何を大切にしているのか
- どんな環境で力を発揮できるのか
- どんな働き方を望んでいるのか
を整理することは、キャリアの再構築につながります。
そして、信頼できる面談者と出会い、心を開いて話せる時間は、
「自分の人生を言葉にする」大切なプロセスです。
もしあなたがこれから転職を考えているなら、
ぜひ面談を“情報交換の場”ではなく、“自己理解の場”として捉えてみてください。
株式会社S.I.Dはそんなサポートをお心がけています。
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
あなたの中にある答えを、アイビーの技法がそっと引き出してくれるはずです。