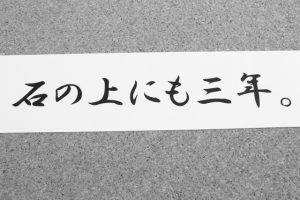目次
1.同一労働同一賃金の概要
2.派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の違い
3.労働者への影響と待遇改善
4.実施に向けたステップ
5.契約書の記載事項と留意点
6.最後に・・・
1.同一労働同一賃金の概要
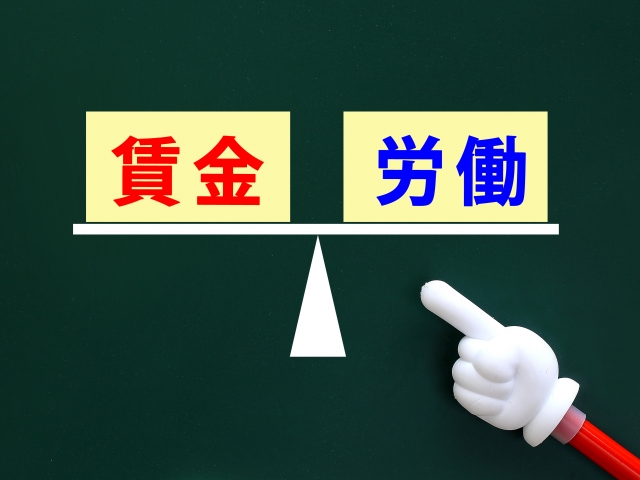
1.1 同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、同じ仕事をしている労働者に対して、正社員・非正規社員(派遣・契約・パートなど)問わず、公平な待遇を求める制度です。2018年の法改正(パートタイム・有期雇用労働法の改正、労働者派遣法の改正)により、派遣労働者も含めた労働者の均等待遇が義務化されました。
具体的には、給与だけでなく、福利厚生、教育訓練、退職金制度など幅広い待遇面で「同一労働には同一の待遇」を求めるものです。これは単なる賃金の比較にとどまらず、労働環境全体の平等性を高めるための制度です。
1.2 法改正の背景と目的
法改正の背景には、日本国内の労働市場における非正規雇用の増加があります。特に派遣社員は、同じ職務を正社員と同じ量・質で行っていても、給与や福利厚生が劣るケースが少なくありませんでした。
この格差を是正するために、厚生労働省は「同一労働同一賃金」の原則を明文化し、企業に対応義務を課す形で法改正が行われました。目的は以下の通りです。
- 非正規労働者の生活安定
安定した収入・待遇により、転職希望者も安心して職場を選択できるようにする。 - 労働市場の公正化
同一労働に対する公平な報酬により、労働者間の不満や離職を減らす。 - 企業の人材活用効率の向上
公平な待遇によって、派遣社員や契約社員のモチベーション向上や定着率向上につなげる。
| 方式 | 実施(義務化) | 法律 |
|---|---|---|
| 労使協定方式 | 2020年4月1日(一般企業) 2021年4月1日(中小企業) | 改正労働者派遣法 |
| 派遣先均等・均衡方式 | 2020年4月1日(一般企業) 2021年4月1日(中小企業) | 改正労働者派遣法 |
2.派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の違い

2.1 方式の本質的な違い
| 方式名 | 誰を基準に待遇を決める? | 賃金の決め方 | 実務の主流 |
|---|---|---|---|
| 派遣先均等・均衡方式 | 派遣先の正社員 | 派遣先正社員の賃金・待遇と比較し、職務が同じなら同等の賃金・手当を支給する必要がある | 実務では“少数” |
| 労使協定方式 | 派遣元(派遣会社)の賃金水準表 | 派遣会社が労働者代表と協定を結び、職種ごとの賃金テーブルを設定する | “圧倒的多数”がこちら採用 |
2.2 派遣先均等・均衡方式
- 派遣先企業の正社員と同じ仕事をする → 同じ待遇にしないといけない
- 正社員と住宅手当・ボーナス・退職金の比較が必要
- 派遣会社は派遣先の正社員の賃金情報を取得しなければならない → ※ここが厳しい
だから派遣元に派遣先企業の賃金フレームの公開をする必要が出てくるため全体の4%ほどのしか派遣先均等均衡方式を採用している企業は少ない状況です。
2.3 労使協定方式
- 企業ごとではなく「職種(例えば:事務/営業/製造オペレーター 等)」に基づき適用最低賃金(=協定時給)を設定
- 協定は労働者代表と合意をとって決める
- ボーナス等も支給方法ルール化できる
- 派遣先の給与情報を取らなくて良い → だからほとんどの派遣会社はコチラを選択
96%以上を占める多くの企業はコチラを採用してます。また「労使協定方式」の方が、賃金構造基本統計調査などを参考にして設定されることが多く、より「ジョブ型採用」に近い制度設計になっているため好まれる傾向が続いています。そのためこの派遣法の改正後、数年が経ちますがこの比率は殆ど変わっていない状況が続いています。
2.4 転職者が理解しておくべき視点
| 観点 | 派遣先均等・均衡方式 | 労使協定方式 |
|---|---|---|
| 扱いの分かりやすさ | 派遣先正社員と同じならわかりやすい | 賃金テーブルの公開の有無で透明度が変わる |
| 給与の底上げのしやすさ | 派遣先が高待遇なら恩恵大 | 全国統計基準なので底割れはしない仕組み |
| 普及率 | 少ない | ほぼ主流 |
ちょっと雑学
ここで言う「均等方式とは?」
- 正社員と同一労働なら同じ給与を支給する方式。
- 基本給だけでなく、賞与・各種手当も含めた比較が必要。
- 簡便ですが、正社員の給与体系に依存するため、派遣社員の柔軟な待遇設定には限界がある。
ここで言う「均衡方式とは?」
- 職務内容や責任の範囲、能力・経験に応じて給与を決定する方式。
- 正社員の給与水準を参考にしつつ、個別の事情に応じて調整が可能。
- 派遣会社や派遣先企業の裁量が大きくなるため、柔軟な待遇設計も可能。
2.5 ここでの結論!
実務では「労使協定方式」がほぼ標準となり「派遣先均等・均衡方式」は制度上はあるが採用企業は少ない状況になります。
3.労働者への影響と待遇改善

3.1 派遣労働者の待遇改善について
法改正により、派遣社員も正社員と同等の待遇を求められるようになったため、以下の改善が進んでいます。
- 給与水準の底上げ
正社員と比較して極端に低い賃金は改善される傾向があります。 - 手当・福利厚生の充実
社会保険や交通費、住宅手当なども正社員に準じて支給されるケースが増加。 - 教育訓練の機会拡大
キャリアアップ支援として、派遣社員も研修や資格取得支援の対象になることがある。
転職者は、これらの待遇改善が実施されている派遣会社を選ぶことで、より安定した収入とキャリア形成が可能です。
3.2 賃金水準の算出方法
派遣労働者の賃金水準は、以下の要素で算出されます。
- 職務内容の評価
正社員との比較を行い、同等の職務であるかを判断。 - 経験・能力の加算
専門性や経験年数に応じた加算。 - 手当・福利厚生の反映
通勤手当、住宅手当、資格手当などの加算を含める。
均衡方式の場合、派遣会社はこれらを総合的に勘案して賃金テーブルを作成します。転職希望者は、派遣会社の賃金算定基準を確認することで、自分の待遇水準を事前に把握できます。
3.3 福利厚生の適用について
派遣社員に対しても、以下の福利厚生が正社員同等で提供されるケースがあります。
- 健康保険・厚生年金保険
- 労働災害補償・雇用保険
- 有給休暇・特別休暇
- 教育訓練制度
ポイントは、福利厚生の適用範囲が契約や労使協定で明示されているかどうかです。転職時には「福利厚生がどこまで適用されるのか」を確認しておくと安心です。
3.4 退職金制度の考慮ポイント
派遣社員は正社員と同等の退職金制度を持たない場合が多いですが、以下のような対応が可能です。
- 派遣会社独自の退職金制度への加入
- 労使協定に基づく積立制度
- 契約期間終了時の一時金支給
退職金制度の有無は、長期的なキャリア形成や生活設計に影響するため、転職希望者は事前に確認しておくことが重要です。
4.実施に向けたステップ

4.1 派遣会社選定のポイント
転職者・求職者は、以下のポイントで派遣会社を選ぶと良いでしょう。
- 派遣先均等・均衡方式や労使協定方式の採用状況
公平な待遇を受けられるかの重要な指標です。 - 賃金テーブルの透明性
どの条件でどの給与が支給されるか明確かを確認。 - 福利厚生や研修制度の充実度
長期的なキャリア形成を支援してくれるかを確認。 - 転職者向けサポート
契約更新や正社員登用のチャンスなど、将来性を見極める材料になります。
4.2 賃金テーブルの作成方法
派遣会社が賃金テーブルを作成する場合、以下のステップで進めます。
- 職務評価の実施
派遣先での職務内容や責任範囲を整理。 - 正社員基準との比較
同等職務の場合、基本給・手当を算出。 - 経験・能力の加味
スキルや経験年数に応じた加算を設定。 - 労使協定の反映
労働者代表との協定に基づき、最低賃金や待遇を決定。
転職者は、賃金テーブルが明確に定められている派遣会社を選ぶことで、待遇の透明性を確保できます。
4.3 従業員教育訓練の必要性
派遣社員も教育訓練の対象となることがあります。理由は以下の通りです。
- 職務の高度化
技術や専門性が求められる職務で必要なスキル向上。 - 正社員との公平性
教育訓練の機会を均等に提供することで、待遇差を縮小。 - キャリア形成支援
転職者や派遣社員の将来の正社員登用やキャリアアップに直結。
教育訓練の充実度も、転職希望者が派遣会社を選ぶ際の重要な判断材料です。
5.契約書の記載事項と留意点
派遣契約書には、以下の事項が明確に記載されているか確認する必要があります。
- 賃金額・計算方法
- 手当・福利厚生の適用範囲
- 契約期間と更新条件
- 労使協定や均衡均等方式の適用状況
転職者は、契約書を確認することで、自分の待遇が法的に保護されているかどうかを判断できます。特に「労使協定方式での賃金算定」や「均衡方式の評価基準」が明記されているかは必須チェックポイントです。
5.1 派遣社員の責任範疇(ここが本質)
派遣社員の責任範囲は 契約で定められた業務の範囲内だけ です。
これがまず大前提。
そしてもうひとつ重要な点は
指揮命令は「派遣先」から受ける
労務管理(契約・処遇など)は「派遣元」から受ける
責任はこの構造で決まります。
分解するとこうなる
| 項目 | 派遣社員の責任は? |
| 業務遂行 | 契約書で定めた業務の範囲内で責任を持って遂行する義務 |
| 指示系統 | 派遣先の指示に従う義務がある (ただし法令違反・安全無視は別) |
| 機密管理 | 派遣先で知り得た情報の秘密保持義務は負う |
| 損害賠償 | 故意・重過失の場合は民法上責任を問われる可能性あり (※日常レベルのミスは一般的には個人負担させられない) |
| 労務トラブルの報告 | 派遣元に報告義務がある(派遣先ではなく) |
責任が “無い” or “原則背負わない” もの
| これは派遣社員の責任じゃない | 理由 |
| 他の社員を指揮・監督する | 指揮命令権は派遣先側にあるため |
| 会社全体の成果に対する責任 | 個人業務範囲の結果責任だけを負う |
| 正社員の代替として組織管理をする | 法的に「代替要員」ではない |
派遣社員に対して、派遣先が「責任押し付け」をするケースはよく見られますが、それは法的にアウト。
あくまで あなたは“契約で定められた業務”の提供者 であり、会社運営責任者ではありません。
一言でまとめると
派遣社員の責任は「契約で決められた自分の仕事の範囲」だけ。
組織責任や管理責任までは負わない。これが派遣社員の責任の範疇です。
6.最後に・・・
派ここで重要なのは、「派遣社員自身がどの方式を使うかを選べるわけではない」という点です。方式を決めるのは派遣会社と派遣先です。だからこそ、求職者や派遣として働く側は面談や登録時、求人応募前の段階で必ず確認するべきなのです。
・その会社は労使協定方式なのか
・その会社は派遣先均等・均衡方式なのか
・賃金テーブルは公開されているか
・賞与・退職金・手当の根拠が明確か
・教育訓練の制度は実態として機能しているか
これらを質問し、説明を受ける権利は労働者側にあります。
方式の「違いを知る」ことは、自分の待遇を守るための防御策であると同時に、キャリアの価値を最大化する攻めの武器にもなります。制度理解と質問の習慣を身につけることで、「派遣だから仕方ない」ではなく「自分の選択で待遇をコントロールする」方向へと意識が変わっていきます。
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
あなたのスキルは、あなたが考えている以上に価値があります。
その価値が正当に扱われる環境を選ぶ力を持つこと。
それこそが、今後の派遣キャリア成功のための最大のポイントです。