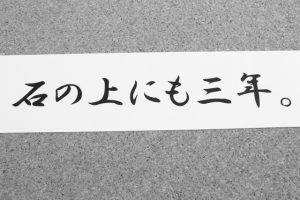目次
1.はじめに ~働き方改革関連法とは~
2.連続勤務の上限規制(連続勤務14日超の禁止)
3.法定休日の明確化義務
4.勤務間インターバルの義務化
5.有給休暇の賃金算定における「通常賃金方式」の原則化
6.カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
7.101人以上の企業に対して、女性活躍に関する情報の公開義務化
8.在職老齢年金制度の見直し
9.ストレスチェックの厳格化
10.副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し
11.最後に・・・
1.はじめに
2026年は、日本の労働・社会保障制度において非常に注目すべき転換点となる年です。厚生労働省を中心に、働き方改革を深化させるための法改正が多数進んでおり、これらは企業だけでなく、私たち労働者にも大きな影響を及ぼします。
本記事では、「働き方改革関連法」を中心に、2026年に予定されている主要な改正ポイントを整理し、特に労働者(正社員・非正規・高齢者を問わず)が知っておくべき内容を詳細に解説します。
改正内容を先取りして知ることで、自分自身の働き方やキャリア、契約内容、就業環境を見直すきっかけになるはずです。
1.1 働き方改革関連法とは
まず前提として、「働き方改革関連法」とは、労働時間の上限規制、年次有給休暇制度の改善、柔軟な働き方の促進など、2019年ごろから段階的に導入された複数の制度群を指します。これらをさらに強化・見直す形で、2026年にも一連の法改正が予定されている状況です。
以下では、具体的な改正のポイントと、その意義・リスク、労働者としてどのように備えるかを、ひとつひとつ見ていきます。
2.連続勤務の上限規制(連続勤務14日超の禁止)

2.1 改正の内容と背景
厚生労働省の研究会報告により、14日を超える連続勤務を禁止する規定を労働基準法に設ける方向で議論が進んでいます。 これは、「労働からの解放(=休息時間を確保するという考え方)」を強化する取り組みの一環です。報告書内でも、心理的負荷や過重労働リスクへの懸念が指摘されており、2週間以上休みなしの勤務が精神的負荷になる例もあるとされています。
2.1 労働者への影響
長時間・連続勤務がある業種(小売・宿泊・飲食・建設など)は特に大きなメリットがありえます。これまで「連続出勤を余儀なくされてきた」現場で、休息が取りやすくなる可能性があります。連続勤務禁止が正式に法律になると、会社が就業規則や勤務シフトを見直す必要が出てきます。労働者側からも、上限を超える勤務を求められた場合には「法違反になる可能性」を根拠に交渉・相談しやすくなる。
2.3 労働者として備えるポイント
- 自分の勤務シフトや就業規則を今のうちに確認しておきましょう。特に連続勤務が常態化している職場では、この改正が実際に適用されるかどうかを注視する価値があります。
- 労働組合や労働相談窓口(労基署・社労士など)を利用して、改正後の勤務パターンがどう変わるかを予測し、自分の「理想の働き方」について社内で提案をしてみるのもよいでしょう。
3.法定休日の明確化義務

3.1 改正の内容と背景
法定休日(休日出勤・休日の定義)の明確化を企業に義務づける議論があります。厚労省の研究会報告では、休日・休暇の扱いをより明確に規定させる必要性が指摘されています。 現行では「4週4休制」などの週単位の休日規定がありますが、連続勤務の上限規制などとあわせて、休日の「確実性」と「構造化(明文化)」が求められています。
3.2 労働者への影響
明確な休日規定があることで、企業は「休日出勤を強要しにくくなる」「休日が取れる保証が強まる」可能性があります。労働者は、自分の休日が法定休日としてきちんと認められているか、就業規則に記載があるかを確認する機会になります。
3.3 備え・アクション
- 就業規則や雇用契約書を確認し、会社が「法定休日」をどのように定義しているかチェックしましょう。
- 会社に確認・相談する際には、「休日とはどの日を指すか」「休日出勤時の賃金(割増・振替)はどうなるか」などを具体的に問いただすとよいです。
4.勤務間インターバルの義務化

4.1 改正の内容と背景
勤務間インターバル制度(前日の終業と翌日の始業の間に一定時間の休息を入れる制度)を義務化する方向が検討されています。 現在は「労働時間等設定改善法」などで努力義務とされており、企業・事業所により任意導入が多いですが、報告書では義務化を視野に入れるべきとの指摘があります。
また、報告書では、「勤務時間外連絡(つながらない権利)」のガイドライン整備を労使で進めるべきという提言もあり、労働時間外の対応への歯止めをかける方向性が示されています。
4.2 労働者への影響
インターバルが義務化されれば、終業後から翌日の始業まで十分な休息時間が確保されやすくなり、疲労蓄積や過労リスクが軽減される可能性があります。特に夜勤・シフト勤務者、交代制勤務者、高負荷業務を行う労働者などにとっては、ワークライフバランスの改善につながる重要な制度です。
4.3 備え・アクション
- 日頃から自分の勤務スケジュール(終業時間・始業時間)を記録し、「休息時間」がどれだけ確保されているかを把握する。
- 就業規則・シフト運用ルールの変更時には、インターバルの導入を企業側に提案・交渉する。特に労働組合がある場合は、制度導入交渉のテーマとして取り上げる。
5.有給休暇の賃金算定における「通常賃金方式」の原則化

5.1 改正の内容と背景
年次有給休暇(有給休暇)を取得した際の賃金算定方法に関して、「通常賃金方式」を原則とする方向が示されています。報告書では、日給・時給の労働者が不利益を被らないよう、「通常の賃金(所定労働時間働いた場合の賃金)」を基準とすべきとの提言があります。従来、一部企業・契約形態では、有給休暇取得時の賃金が「最低限」の額に抑えられていたり、特殊な算定基準が使われていたケースもあり、労働者保護の観点からの改善が求められています。
| 2026年以降 | 計算方式 | 内 容 |
| 〇 | 通常賃金 | 労働者が通常どおり勤務していれば支払うことになる賃金。 |
| ✖ | 平均賃金 | 直近3ヶ月の労働日数に基づいて計算される賃金。 |
| ✖ | 標準報酬月額 | 標準報酬日額: 健康保険料の基準となる標準報酬月額を30で割った金額。 |
5.2 労働者への影響
有給休暇を取ったときに支払われる賃金がこれまでより高くなる可能性があり、有給取得への心理的・経済的ハードルが下がります。特にパート・アルバイト・時給制労働者にとっては、有給取得が会社への「損」と感じられにくくなり、休暇の取得が促進されやすくなる期待があります。
5.3 備え・アクション
- 自分の賃金形態(時給、日給、月給等)と有給休暇取得時の賃金がどう算出されているかを確認。就業規則や賃金規定を見てみましょう。
- 有給取得をする際、「有給を使っても賃金が減らない(または少なくしか減らない)」ことを根拠に、会社に交渉・確認をする。必要であれば労働相談窓口を利用。
6.カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化

6.1 改正の内容と背景
2025年6月に「労働施策総合推進法」が改正され、**顧客等からのハラスメント(カスタマーハラスメント、略して“カスハラ”)への事業主義務(雇用管理措置義務)**が新設されます。
定義としては、
(1)顧客・取引先などが行う
(2)社会通念上許容される範囲を超える言動
(3)就業環境を害するものが対象。
企業には「相談体制の整備」「方針の明文化・周知」「発生後の迅速かつ適切な対応」などが義務付けられる見通しです。 また、会社が被害相談した労働者に不利益取扱い(解雇など)をしないよう保護する規定も明確化される可能性があります。
6.2 労働者への影響
特に飲食業、小売業、サービス業、医療・福祉など、顧客対応が頻繁な職場では、従業員の精神的な負担が軽減される可能性が高まります。カスハラ対応が制度として義務化されれば、「我慢が必要」「仕方ない」とされてきた理不尽な顧客対応に対して、会社に相談しやすくなります。
6.3 備え・アクション
- 自分の職場で、カスハラ対策の相談窓口・仕組みがあるか確認する。
- 実際に理不尽な対応を受けた経験がある場合は、記録(日時、内容、やり取りなど)をつけ、証拠を残す。制度発効後に問題を訴える際に有効になります。
- 労働組合や労働者代表(過半数代表など)があれば、カスハラ対策を就業規則・内規に盛り込むよう働きかけをする。
7.101人以上の企業に対して「女性活躍に関する情報」の公開義務化

7.1 改正の内容と背景
女性活躍推進法が2026年に改正され、常時雇用する労働者が101人以上の企業に対して、男女間の賃金差異や女性管理職比率などの情報の公表が義務化されます。 従来は301人以上の企業が対象だった情報公表義務を大幅に拡大する改正であり、企業の透明性を高め、女性のキャリアを後押しする狙いがあります。
公表項目には、「男女の賃金の中央値の差」「管理職比率」「職種転換・雇用形態の転換実績」などが含まれており、企業はデータを把握し行動計画を策定・公表する必要があります。
7.2 労働者への影響
101人以上の企業に勤めている労働者(とくに女性)は、自社の男女賃金格差・管理職比率を知ることができ、自身の昇進・キャリアパスを考える際の判断材料が増えます。情報公開によって、企業への改善圧力が高まり、女性がキャリアを築きやすくなる可能性があります。
7.3 備え・アクション
- 自社が従業員100人以上(またはそれに近い)規模であれば、情報公開に関する社内の取り組みを注視しておく。
- 公表されたデータ(賃金格差、管理職比率など)を見て、自分のキャリア形成や待遇交渉の材料とする。
- 社内で女性活躍や賃金格差是正のための意見交換(労働組合、社員ネットワークなど)があれば、積極的に参加・発言する。
8.在職老齢年金制度の見直し

8.1 改正の内容と背景
在職老齢年金(いわゆる「働きながら年金を受け取る高齢者向け制度」)の支給停止基準額が2026年4月から月額62万円(2024年度価格)に引き上げられる予定です。
現行制度では、賃金と厚生年金の合計が基準額(50万円~51万円)を超えると、その超過分の年金が半分停止されるルールでした。 基準額を62万円に引き上げることで、在職高齢者がより多く働きつつ年金を満額受給しやすくなることが見込まれています。 背景には、高齢者の就労意欲を下げないこと、人手不足対策として高齢社員を活用しやすくする意図があります。
8.2 労働者への影響
60歳以上・65歳以上など、高齢で働いている・働こうとしている人にとっては、働きながら年金を受ける選択肢がより現実的になります。「働いたら年金が減る=得にならない」というジレンマが和らぎ、「収入を落とさず働き続ける」モチベーションになり得ます。企業側も高齢人材の継続雇用・再雇用を進めやすくなり、スキル継承や人員確保の観点からプラスになる可能性があります。
8.3 備え・アクション
- 自分が在職老齢年金の対象になるかどうかを確認(年齢、報酬額、年金額など)。年金相談窓口や社会保険労務士に相談して、自分の場合の支給停止額の見込みを把握する。
- 年金受給と就労を両立する際のキャリアプランを立てる。無理なく働き続けるか、ペースを落とすか、休みを増やすかなどを考えてみましょう。
- 会社の人事・労務担当者と話して、高齢者の雇用条件(給与、勤務時間、役割など)を相談し、在職年金を前提とした待遇設計を交渉する。
9.ストレスチェックの厳格化

9.1 改正の内容と背景
労働安全衛生法が改正され、ストレスチェック制度が従業員50人未満の事業所にも義務付けられる見込み。
これまでは50人未満の事業所では努力義務であったストレスチェックですが、改正後は規模を問わず義務化されるため、多くの中小企業・小規模事業所にも影響があります。 小規模事業場の費用や運用の負担にも配慮されており、導入準備期間を確保することなども法改正案に含まれています。
9.2 労働者への影響
ストレスチェックが義務化されることで、メンタルヘルスの自己認識を高めやすくなります。労働者自身がストレスの兆候を早期に把握し、適切なケアを求めるきっかけとなります。組織としてストレスチェック結果の「集団分析」が行われやすくなり、職場環境改善への動きが出やすくなります。
結果をもとに、労働者側が「業務負荷」「勤務体系」「支援体制」などについて会社に要望を出す正当性が強まります。
9.3 備え・アクション
- 自分の職場でストレスチェックがどう運用されているかを確認。チェックを実施する時期、頻度、フィードバック方法などを把握しておきましょう。
- ストレスチェック後の面談制度やケア制度があるかを確認し、必要であれば利用を躊躇しない。相談窓口(産業医、保健師、人事担当など)を事前に把握しておく。
- 組織改善を目指す場合、ストレスチェック結果を根拠に「改善提案」をする。過度な業務負荷や長時間勤務、勤務スケジュールなどについて具体的な改善案を提示する。
10.副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し

10.1 改正の内容と背景
研究会報告などで、副業・兼業者に対する割増賃金の算定において 労働時間の通算ルールを見直す議論が出ています。 これまでは、異なる勤務先(副業先・兼業先)で働いた時間を通算しない、または通算が難しいケースがあり、それが不公平や複雑性を生んでいたとの指摘があります。 見直しによって、複数事業所間での勤務をしている労働者が、割増賃金の適正な支払いを受けられるようにする狙いがあります。
10.2 労働者への影響
副業・兼業をしている人にとって、時間外労働や休日労働の割増賃金がきちんと支払われる可能性が高まる。副業を理由に「残業代がつかない」「時間管理が不利になる」といったリスクが軽減される。自分の働き方に応じて、時間を計画的に使いやすくなる。たとえば、本業・副業を通じて収入を最大化できるような交渉材料になる。
10.3 備え・アクション
- 副業・兼業をしている、または検討しているなら、現在の就業契約書をよくチェックし、残業・休日勤務の取り扱いを確認。
- 複数の勤務先間で時間を通算した場合の割増賃金ルールを会社に質問・確認しておく。
- 将来的な法改正を見越し、副業契約を結ぶ際には、時間の管理や割増支払いについて明文化を求める。必要であれば労働相談窓口を活用。
11.最後に・・・
2026年は、働き方改革がさらなる段階へ進む重要なタイミングです。今回紹介した改正ポイントは、労働者の健康・ワークライフバランス・収入・キャリアのすべてに関わるものばかりで、私たち自身の働き方を見直す絶好の機会でもあります。
- 自分の働き方を振り返る :スケジュール、賃金形態、役割、キャリア目標などを再確認しましょう。
- 情報をキャッチアップする:会社からの法改正通知、就業規則改訂、労働組合や社内ネットワークの動きを注視。
- 主体的に交渉・提案する :勤務制度や就業規則の改善を働きかける。休息時間・休日・メンタルケアなど、自分や
同僚のための具体的な提案を一緒に協議する。 - 専門家を活用する :労働相談窓口、社労士、年金相談所等を活用し自分の状況に即したアドバイスを受ける。
これらの改正は、単なる「制度の変化」ではなく、私たち労働者がより安心・安全に、そして意欲的に働ける社会づくりの一歩です。自分の働き方を自分でコントロールするために、今から準備を始めましょう。
株式会社S.I.Dはそんな働く皆さんを応援しています。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
最新の法改正の情報を知ることで、
働きやすい職場の実現を一緒に目指しましょう!