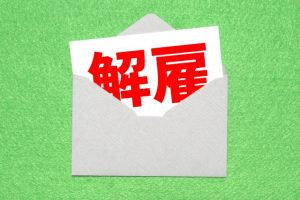目次
1.心を通わせる退職相談の意義
2.退職相談を受ける際の具体的な方法
3.上司として退職相談での有効な伝え方
4.部下が辞める際の上司の役割
5.引き止めない姿勢の重要性
6.部下のキャリア支援の方法
7.心構えと注意点
8.最後に・・・
1.心を通わせる退職相談の意義

1.1 上司としての心構えと準備
部下から退職の相談を受けたとき、多くの上司は驚きや戸惑いを覚えることでしょう。しかし、その瞬間こそ、上司としての力量や信頼関係が問われる重要な場面です。
まず大切なのは、「冷静さを保つ」ことです。突然の申し出に動揺したり、感情的に反応してしまうと、部下との信頼関係にひびが入る可能性があります。退職という重大な決断には、それなりの覚悟や理由があります。上司はその背景を真摯に受け止める準備が必要です。
また、退職相談は単なる報告ではなく、「対話の機会」でもあります。部下がこれまで抱えていた悩みや、今後の展望を聞き出すことによって、より良い関係性を築くきっかけになります。上司として、部下の声にしっかりと耳を傾け(傾聴)、共感を持って向き合う姿勢が求められます。
1.2 部下が辞める理由とその受け止め方
退職理由は人それぞれであり、個人のキャリア志向、職場環境、人間関係、待遇、家庭事情など多岐にわたります。中には本音を語らないまま表面的な理由にとどめるケースもありますが、重要なのはその背景を「批判ではなく理解」の視点で受け止めることです。
たとえば「もっと成長できる環境に行きたい」「給与が見合わないと感じる」などの理由があった場合、それは現職の改善点に気づかせてくれる貴重なフィードバックにもなります。個人の選択を尊重しつつ、上司としては職場の在り方を見直す機会と捉えることが大切です。
1.3 円満退職を実現するための配慮
円満退職とは、本人と会社の双方にとって納得できるかたちでの退職を意味します。その実現には、以下のような配慮が欠かせません。
- ネガティブな反応を避ける
退職の意思を聞いたとき、感情的になって責めたり、皮肉を言ったりするのは厳禁です。 - 引き継ぎの重要性を説明する
業務への影響を最小限に抑えるために、適切なスケジュールで引き継ぎを進めることの大切さを伝えましょう。 - 周囲への配慮も促す
同僚への影響や、社内のモチベーション低下を防ぐための情報開示のタイミングや方法について、本人と相談します。
無暗に話が広がってしまうと慰留が出来たとしても、相談者本人が残りづらくなります。 - 感謝の気持ちを伝える
最後まで前向きな関係性を保つために、「これまでの貢献に対して感謝する」姿勢がとても大切です。
2.退職相談を受ける際の具体的な方法

2.1 部下とのコミュニケーションの工夫
退職相談においては、「どう聞くか」「どこで聞くか」「どのような雰囲気で進めるか」が非常に重要です。
- 場所の配慮:静かで第三者の目が届かない会議室などを選びましょう。
- 時間の確保:10分や15分の空き時間で済ませようとせず、しっかりと時間を確保して対応します。
- 傾聴を重視:口を挟まず、まずは相手の話を最後まで聞き切る姿勢が信頼に繋がります。
また、「なぜ辞めたいのか」ではなく、「どうしてそう思うようになったのか」という問いかけにすることで、部下の本音に近づくことができます。相談開始時には、必ずしも部下は本音を言っているとは限りません。辞めたい理由を本音と建前で使い分けていることもありますし貴方自身に原因があった時には別の理由で退職理由を話してくることもあるでしょう。
聞き方(傾聴)としては
「相談してくれてありがとう。その辞めたくなるほどの悩み事についてもっと詳しく聞いてもいいかな。きっかけは・・」
など、過去の出来事や気持ちの変化を時間軸で聞き出すことが、上司としての気づきにもなります。
2.2 退職の意思決定に関する確認事項
部下が「退職したい」と言ったからといって、すぐに決定事項として受け取るのは早計です。
まず確認したいのは、
- 退職意思の固さ
一時的な感情や、誰かとのトラブルなどで勢いづいていないか。 - 転職時期
「今すぐにでも」という人もいれば「来年の3月に」など人によっては前もって相談してくるケースもあります。
慌てず・騒がず、「いつ頃なのか?」「何故その時期なのか?」も面談の中で傾聴しましょう。 - 家族や私生活の問題や理解度
原因は仕事だけとは限りません。私生活での問題やトラブルは仕事のパフォーマンスに大きく影響します。
本人だけでなく周囲のサポート体制も考慮に入れましょう。両親の介護で離職を余儀なくされる方も一定数居ることも事実です。 - 代替案の有無
配置転換、役割の見直し、働き方の変更などで状況が改善する可能性がないか。
家庭の問題などについては妥協点や代替案を見いだせる可能性が大いにあります。
また、話し合いを1回で終わらせず、「一度持ち帰って考えてみようか」と時間を置くことも有効です。人は話すことで思考が整理されますし、冷静になる時間が状況の再考を促します。この際、次の面談日の日時を決めておくことも重要です。
相談者側は相談することに自体に不安感や信頼関係が揺らいでいます。次回の面談日を決めずに終わらせると相談者は「放置されている」、「この人に相談しても理解して貰えなかった」、「気持ちを伝えても無駄だった」という諦めに近い心境になります。これはモチベーションを大きく下げ、突発退職にもつながる大きなリスクが発生します。
次の面談日を決めておくことで双方に取って客観的に見つめ直す時間と改善できる猶予期間を持つことができます。そして何より、突発退職を未然に防ぐ効果も生まれます。
ポイントはココ!
- 時間軸で辞めたくなった背景を遡り時系列で原因を分析
本人自身が辞めたいと感じたきっかけや出来事を時系列ごとに話して貰いましょう。 - 相談者からの主訴を明確にしておく
退職を申し出ている時の相談者は心に不安と葛藤で心身共に混乱をしていることも。沢山の不安や悩み事の中から要因では無く、根本的な原因を見つめてあげましょう。相談者は本人自身が辞めたいと感じている根本原因を理解していないケースもあり。 - 相手の会話や発言は祭儀らない(傾聴する)
あくまでも相談者本人の気持ちを全て吐き出させることが重要です。本人の想いを遮ってしまうと「この人に相談しても理解して貰えない」と相談者は心を閉ざしてしまいます。 - 次回の面談日時を決めておく
次回の面談日時を決めておくことで時間的猶予と客観的に見つめ直す時間が生まれます。また、突発退職の抑止力にもつながります。
2.3 引き継ぎに必要なスケジュール管理
退職が正式に決まった場合は、速やかに引き継ぎスケジュールの作成に着手します。
引き継ぎは後任者への知識移管だけでなく、組織の信頼性を保つための重要プロセスです。
- 引き継ぎリストの作成
業務の棚卸しを行い、担当しているタスクのリスト化と優先順位付けを行います。 - 後任者選定と教育計画
適任者を早期に選出し、OJTの計画を立てます。 - 最終日までのスケジュール表
いつ何を行うかを明確にした工程表を共有し、部下と進捗を確認していきます。 - 関係者への周知
取引先や関係部署への挨拶・引き継ぎのタイミングなども含め、周囲に迷惑をかけない配慮が必要です。
退職者にとっても、最後にしっかりと引き継ぎを終えることは、社会人としての信頼を高める行為でもあります。その意味を上司が丁寧に伝えることが、円満な最終日につながります。
3.上司として退職相談での有効な伝え方

3.1 上司への報告の適切なタイミング
退職の報告は、適切なタイミングで伝えることが円滑な対応を生みます。理想的には「退職希望日の1〜2か月前」が一般的ですが、業務内容や立場によっては3か月以上前に伝えるのが望ましい場合もあります。
また、上司が多忙でない時間帯、たとえば午前中や夕方前など、集中して話せるタイミングを選ぶことも大切です。会議前後、直前に話しかけるのは避けるのが賢明です。
退職の話は心理的に重たいテーマのため、部下からすると伝えづらい内容です。上司としては、「何か困っていることがあればいつでも相談して」といった日頃の関係づくりが、こうしたタイミングの適切化に繋がります。
3.2 感情に配慮した言葉の選び方
退職相談において、上司が発する言葉は相手の心理に大きな影響を与えます。まずは否定や決めつけを避け、次のような表現を心がけましょう。
- 「そうだったんだね、まず話してくれてありがとう」
- 「悩んだ末の決断なんだね。どんな気持ちでそう思ったのか、聞かせてくれる?」
- 「これまでの頑張りはよく見ていたよ」
一方、以下のような言葉は避けるべきです。
- 「このタイミングで辞めるなんて無責任だ」
- 「こんな待遇で不満なら、どこ行っても同じだよ」
- 「誰かにそそのかされたんじゃないの?」
感情的な発言や皮肉を含んだ言葉は、部下との信頼を損ない、円満な退職を遠ざける結果になります。
3.3 相談なしの退職への対応策
「退職届を突然提出された」「全く相談もなく辞める意思を伝えられた」──そんなケースも少なくありません。その背景には、「上司が話しやすい雰囲気を作れていなかった」「以前の相談時に否定的な対応をされた」などが隠れている可能性があります。
対処方法としては以下のステップが有効です。
- 感情的に反応しない :まずは冷静に話を聞く姿勢を持つ。
- 退職理由の確認 :急な意思表示に至った理由を丁寧にヒアリング。
- 事後フォローの体制確認:業務の穴埋めと引き継ぎへの協力依頼。
- 振り返りの実施 :なぜ相談しづらかったのか、組織やマネジメント体制の課題を洗い出す。
また、日頃から「気になることは早めに相談して良い」といった風通しの良い職場風土を育てることが、こうした突発的な退職を未然に防ぐポイントです。
4.部下が辞める際の上司の役割

4.1 後任をどうするかの提案
部下の退職が決まった際、まず直面するのが「誰が後任を担うのか?」という課題です。上司は単に人を補填するだけでなく、業務の継続性とチーム全体への影響を最小限に抑える配慮が求められます。
1. 後任選定のポイント
後任は必ずしも「年次が上」や「経験が長い人」だけが適任とは限りません。以下のような観点から総合的に判断することが重要です:
- 現在の業務の理解度
- 周囲との協調性
- 意欲と将来性
- 本人のキャリア希望や成長意欲
必要であれば一時的に役割分担制を導入し、数人で分担しながら育成していく体制を組むのも有効です。
2. 外部採用も視野に入れる
内部だけでは対応しきれない場合は、派遣社員や中途採用など外部リソースの活用(業務委託や外注化、システムの導入など)も選択肢に含めましょう。仕組化や即戦力を採用することで、業務負荷を抑えつつ組織のパフォーマンス低下を回避できます。
3. 本人へのヒアリングと連携
退職者本人に後任候補の引継ぎを相談するのも良い方法です。本人が信頼する同僚や、適性のあるメンバーに対し、
「この部分は○○さんが適任だと思います」
「この人にはこの資料を教えておきたいです」
といった意見を引き出すことで、引継ぎの精度が向上し、本人も安心して退職できる環境を整えられます。
5.引き止めない姿勢の重要性
上司としては、「辞めないでほしい」と思うのが本音かもしれません。しかし、引き止めることが必ずしも本人や組織のためになるとは限りません。本人が納得感の無いまま慰留をさせてしまうと、次に大きな波ととして退職したいという気持ちに襲われることが多くあります。「あなたの存在価値や重要性」を伝えることはとても重要ですが、誤った認識は組織として崩壊する恐れもあります。誇張や本人の誤った自己評価(過大評価や過小評価)は慰留できたとしても双方が不幸になることもあります。
5.1 強引な引き止めが招く悪影響
- 退職希望者が「情で縛られた」と感じてしまう
- 本人の成長やキャリアを阻害してしまう
- 引き止められた後もモチベーションが下がり続ける
- 周囲の社員に「結局辞められない空気」が伝播する
など、組織風土にもマイナスの影響を与えかねません。
5.2 「引き止めない姿勢」は信頼の証
部下の退職を尊重する姿勢は、**「この人になら本音を話せる」「自分の判断を受け止めてくれる」**という上司としての信頼にもつながります。
どうしても残ってほしい理由がある場合でも、「一度持ち帰ってじっくり考えてみてください」と選択肢を与えるスタンスを忘れないようにしましょう。
5.3 引き止めるべき例外とは?
ただし、以下のようなケースでは慎重な引き止めも検討の余地があります。
- 感情的に辞意を示している(勢いでの退職)
- 人間関係の一時的なトラブルによる退職
- 業務上の行き違いや誤解による退職希望
このようなケースでは、原因をクリアにし、本人の意思を再確認した上で話し合うことが肝心です。
6.部下のキャリア支援の方法
退職は一つの終わりではなく、新しいキャリアのスタート地点です。上司は、在職中だけでなくその後も見据えたキャリア支援を行うことで、本人にとっても組織にとっても価値のあるサポートになります。
6.1 キャリアの棚卸しをサポートする
退職相談を受ける際には、ただ聞くだけでなく
「この仕事で身につけたスキルは、今後も活かせるよね」
「これまでの経験はどんな場面で役立ったと思う?」
といった質問を通して、本人のキャリアの棚卸しを手伝うことができます。これは、自己肯定感を高める効果もあります。
6.2 自信を持たせる声かけ
たとえば以下のような声がけは、退職者にとって大きな支えになります。
- 「新しい挑戦、応援してるよ」
- 「ここで頑張っていた姿は忘れない」
- 「また何かあったら気軽に連絡して」
特に若手や初めての転職者にとっては、背中を押してくれる存在がいることが安心感につながります。
6.3 キャリアパスの相談に乗る
もし可能であれば、本人の希望業種や職種についても話を聞きながら、
- 「この分野の人材には、こういうスキルが求められるらしい」
- 「転職エージェントに相談してみるのもいいかもね」
など、次のステップに向けた具体的なアドバイスも加えると、より手厚い支援となります。転職の意志が固いのであれば、時には推薦状を書いてあげるのも1つ。本当に部下の幸せや成功を祈る気持ちがあるのであれば心から応援してあげましょう。
7.心構えと注意点

7.1 自分の責任を考慮することの重要性
部下が退職を申し出るという出来事は、単なる「個人の選択」として済ませるべきではありません。もちろん、すべての退職理由が上司や会社に起因するわけではありませんが、「自分の関わり方が退職を早めた可能性はないか?」という内省は不可欠です。特に近年では、マイクロマネジメントや感情的な言動によるストレスが、若手社員の退職要因として注目されています。
退職という結果が出た後でも、自分のマネジメントスタイルを振り返ることは、今後のチーム運営や部下との信頼構築に活かせます。例えば「裁量を与えていたか」「話を聴く姿勢を持てていたか」「評価や承認の伝え方に偏りはなかったか」など、具体的な場面を想起しながら振り返ることで、自己成長にもつながります。
大切なのは「自分を責める」ことではなく、「改善の機会」として前向きに捉えること。退職という出来事を、チーム全体のより良い未来につなげるチャンスとする姿勢が、真に信頼される上司への道を切り開きます。
7.2 部下の不安に寄り添う姿勢
退職を申し出る部下の心境は、外から見えるよりも複雑です。「この決断で本当に良いのか」「裏切りと思われないか」「周囲との関係が悪くならないか」など、多くの不安を抱えています。だからこそ、退職相談を受けた上司の「寄り添う姿勢」が極めて重要です。
寄り添うとは、「同意すること」ではありません。「話を否定せずに受け止める」「理解しようという姿勢を見せる」「感情に巻き込まれず、冷静かつ温かい態度で応じる」といった行動が該当します。特に注意したいのは、以下のような態度です。
- 「裏切られたように感じる」と言ってしまう
- 「どうせどこへ行っても同じだよ」と相手の選択を否定する
- 「本当に辞めたいの?」と問い詰めるように言う
これらはすべて、相談者の不安を増幅させ、円満退職から遠ざける結果となります。
一方、「まずは話してくれてありがとう」「悩んだ末の決断なんだね」といった言葉がけは、部下に安心感と信頼を与えます。退職という決断が確定していたとしても、「相談してよかった」と思わせる対応が、上司としての価値を高めるのです。
7.3 退職を受け入れる勇気と方法
部下の退職は、チームにとっても上司にとっても痛手です。戦力ダウン、業務の引き継ぎ、モチベーションの低下など、現実的なデメリットは無視できません。しかし、上司には「退職を前向きに受け入れる」という、もう一段上の対応力が求められます。
退職を“敗北”と捉えれば、どうしても引き止めたり、感情的になったりしてしまいます。しかし、「キャリアの一つの節目」「より良い選択を後押しできた」と捉えることで、部下との関係も、周囲の士気も良い形で保てます。
受け入れのプロセスとして、以下の3つを意識すると良いでしょう。
- 決断を尊重する : 「よく考えた上での決断なんだね」と言葉にする
- 感謝を伝える : 「今まで本当にありがとう」と、労いを明確に伝える
- 送り出す姿勢を示す: 「次の場所でも頑張ってね」と前向きに背中を押す
これらを実践することで、退職者自身だけでなく、チームメンバーの上司への信頼も高まります。「うちの上司は、ちゃんと人のキャリアを考えてくれる」という認識は、組織にとっての大きな財産になるのです。また、部下としてもこの人からもっと多くの事を学べるのではないかと評価を勝ち取ることが出来たら本人も継続して働く動機(モチベーション)が生まれ退職を考え直すこともあります。また残った部下からの評価も上がり部下との信頼関係の構築にも繋がります。
7.4 本当に辞めて欲しくない部下には退職後もフォローを継続
上司の立場としては「辞めた部下より残った部下を優先的にフォロー」をすることは当たり前ですが、一方で特に優秀で本当に辞めて欲しくない部下に対しては退職後もフォローやしっかりしたサポートを行ってあげることをお勧めします。
転職後の職場に必ずしも満足するとは限りません。プラスもあればマイナスもあるように転職後に後悔をしているケースは統計上11%となります。10人に1人は後悔している計算になります。この時にアルムナイ採用を行うチャンスです。
- 理由①
転職後の職場に必ずしも満足するとは限りません。
転職を後悔している部下にはそっと手を差し伸べてあげましょう。 - 理由②
有給消化後も分からない部分や引継ぎ漏れなどのトラブルが起きることは多少なりとも発生します。
その際に関係性が継続していると協力得ることが出来たりスムーズに確認を行うことが出来ます。 - 理由③
「自身の退職面談はどうだったのか」、「本当はどうして欲しかった」相談者本人からフィードバックを貰うことができます。これは次に同じこと様な要因での退職相談の際に有意義な経験となります。
また退職した部下が同業種に転職する事や今後、新規取引先に転職するというケースもあります。**ビジネス上での【人脈を広げる】**という観点からみてもプラスに捉えることが出来ます。
8.最後に・・・
部下からの退職相談は、上司にとって決して簡単な出来事ではありません。動揺や戸惑い、時には悔しさや寂しさを感じることもあるでしょう。しかし、その瞬間こそが、上司としての真価が問われる重要なターニングポイントです。
本記事で述べてきたように、退職相談をただの「報告」として扱うのではなく、「対話の機会」として真摯に向き合うことで、部下との信頼関係はむしろ深まります。円満退職を実現するための準備やコミュニケーション、感情への配慮は、部下の人生を尊重するだけでなく、組織の健全な運営にも直結するのです。
また、退職を受け入れる勇気を持つこと。これは決して「負け」ではなく、部下の未来を応援し、より良いキャリア形成を支援することに他なりません。部下の退職を通じて、自らのマネジメントスタイルを見直すことも、上司としての成長につながります。
最後に、円満な退職を迎えた部下との良好な関係は、その後の人生においても大切な財産です。ビジネスパートナーとして再会したり、思わぬ場面で助け合うこともあるでしょう。だからこそ、誠実で丁寧な対応を心掛け、ポジティブな別れを迎えられるよう努めてください。
退職相談は「終わり」ではなく、新たなスタートの始まりです。上司としてのあなたの対応が、部下の未来と組織の未来を大きく左右します。実際に部下が辞めるとなると、日々の業務に追われるあなた自身にも相当な負荷が掛かると思います。
「そこまでのフォローはちょっと・・・」、「退職者が複数名いて時間的に難しい」など時期やタイミングが重なることもありそこまでのサポートが出来ない事もあるかもしれません。そんな時は信頼できるキャリアコンサルタントを紹介してあげるだけでも違います。私達、株式会社S.I.Dはそんなサポートを心がけています。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
どうか本記事の内容を参考に、心を通わせる退職相談を実践してください。
転職される部下にも、そしてあなたにも幸あれ。