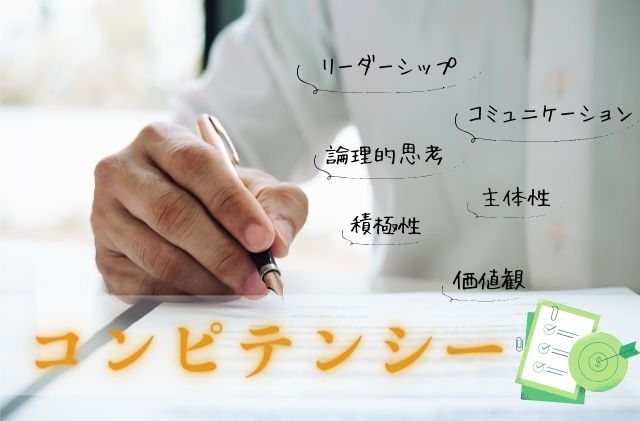目次
1.コンピテンシー面接とは?基本の理解を深めよう
2.STARモデルの解説
3.面接官が重視する評価基準
4.候補者の行動を探るための手順
5.コンピテンシー面接の導入と実践
6.新卒、中途、公務員、各職種への適用
7.注意すべきポイントと一般的なミスマッチ
8.最後に
1.コンピテンシー面接とは?基本の理解を深めよう
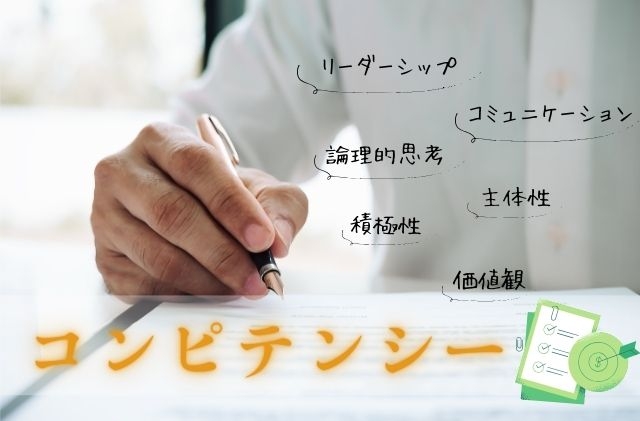
1.1 コンピテンシー面接の定義と重要性
「コンピテンシー面接」とは、応募者の過去の具体的な行動に焦点を当て、それが職務上必要とされる能力(=コンピテンシー)とどの程度一致しているかを判断するための面接手法です。従来の面接が「やる気はありますか?」「長所・短所は?」といった抽象的な質問を軸にしていたのに対し、コンピテンシー面接は「実際にやったこと」に着目し、より客観的かつ実証的な評価を可能にします。
多くの企業がこの面接手法を導入している理由は明確です。単に「話し上手」なだけの応募者を避け、真に実力ある人材を見極めたいというニーズが高まっているからです。
従来の面接との違い
| 項目 | 従来型面接 | コンピテンシー面接 |
| 主な質問内容 | 志望動機、長所短所など | 実際の行動や経験に関する質問 |
| 評価の軸 | 印象・態度 | 実績・再現性のある行動 |
| 質問形式 | 一般的・抽象的 | STARモデルに沿った具体的質問 |
| 判断の基準 | 面接官の感覚 | 行動特性・再現性の有無 |
1.2 コンピテンシー面接のメリットとデメリット
メリット
- 客観性が高く、面接官によるバイアスが少ない
- 応募者の実力やポテンシャルをより正確に把握できる
- 再現性の高い行動に注目することで、入社後の活躍予測がしやすい
デメリット
- 応募者にとって準備が難しい
- 面接官にもトレーニングが必要
- 実績の少ない若手(新卒など)には不利な面がある
2.STARモデルの解説

2.1 STARモデルの構造:Situation, Task, Action, Result
コンピテンシー面接の核心にあるのが「STARモデル」です。これは、以下の4つの要素で構成されます:
- S(Situation):状況
- どのような状況で問題が発生したか
- 背景や課題の環境
- T(Task):課題
- あなたが任された具体的な仕事や目標
- A(Action):行動
- 課題に対して、どんなアクションをとったか
- R(Result):結果
- その行動の結果、どんな成果や学びがあったか
この構造に沿って話すことで、聞き手に伝わりやすく、かつ論理的な自己アピールが可能になります。
2.1 STARモデルの活用方法と効果
STARモデルは以下のように活用できます。
- 面接官の質問に対して的確に答えられるように、事前にエピソードを整理
- 自己PRや志望動機でもSTARを意識して語ると説得力が増す
- 「あなたの強みを教えてください」→「強みを発揮したエピソード」で答えることで、主張の裏付けになる
STARモデルは「話し方の型」でもありますが、それ以上に「行動の棚卸し」をするためのツールとしても優れています。
感じる?STARモデルの実績と成功事例
多くの大手企業がコンピテンシー面接とSTARモデルを導入しています。たとえば
- **P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)**では、
「リーダーシップ」「主体性」「結果志向」などをSTAR形式で評価し、社内でも評価フレームとして定着。 - アクセンチュアやマッキンゼーなどの外資系コンサルも、STARを使って応募者の「構造的思考力」を見ています。
2.2 効果的な質問例で準備を万全に
新卒向け質問例:どのように答えるべき?
新卒採用では、社会人経験がないため「行動実績」が乏しいと思われがちですが、大学生活やアルバイト、ゼミ、部活動など、行動の場は数多く存在します。以下は、新卒向けの質問例とSTARを使った回答例です。
質問例:
「チームで困難な課題に取り組んだ経験を教えてください。」
回答例(STAR形式):
- S(Situation)
大学のゼミで、卒業論文の共同研究プロジェクトを実施していました。 - T(Task)
研究資料の英語文献が多く、チーム内で読む力にばらつきがあったため、役割分担が難しい状況でした。 - A(Action)
私は英語が得意だったため、重要文献の要点を日本語にまとめてチームメンバーに共有し、知識のギャップを埋めるサポートを行いました。 - R(Result)
結果として、研究発表で高評価を得ることができ、教授からも「チームの連携が非常に良かった」とコメントをいただきました。
新卒の場合、「スキル」ではなく「行動特性」が問われることが多いため、誠実さ、主体性、協調性などを意識して答えることが重要です。
公務員向け質問例:特徴を押さえた対策
公務員採用におけるコンピテンシー面接は、「公平性」「倫理観」「協調性」「課題解決能力」など、公共性を重んじた視点で評価されます。
質問例:
「立場の異なる人たちと協力して課題を解決した経験はありますか?」
回答例(STAR形式):
- S:自治体の学生ボランティアに参加し、地域住民との交流イベントを企画しました。
- T:住民の年齢層が高く、ITを使ったイベント案に対して反発もありました。
- A:私は住民と直接話し合い、アナログ的な展示や手書きメッセージの交流スペースを提案し、双方の理解を得ながら内容を再構築しました。
- R:イベントは好評で、来場者数も目標を上回りました。自治体からも継続実施の依頼を受ける成果を得ました。
公務員試験では、面接も「行動特性の一貫性」が重視されるため、誠実な対応や説明責任が含まれた行動を語ることがポイントです。
2.3 評価シートを基にした質問項目の作成
企業によっては、事前に定められた評価シートをもとに質問が設計されます。たとえば以下のような項目が挙げられます。
| 評価項目 | 代表的な質問例 |
| 主体性 | 困難な状況で自ら動いた経験は? |
| 協調性 | チーム内での対立をどう乗り越えたか? |
| 顧客志向 | 顧客の期待を上回る対応をした経験は? |
| 論理的思考 | 問題をどのように分析し、どのような解決策をとったか? |
このような評価シートに基づく質問では、応募者の回答が直接「数値化」され、他候補者と比較されるため、より具体的なエピソードで構成されるSTAR回答が有効です。
一般的な質問からのケーススタディ
以下はどの業界・職種でもよく出る質問例と、それに対する構成のポイントです。
- 「失敗した経験と、そこから何を学んだか」
→ 失敗を恐れずに挑戦した姿勢と、その後の改善行動に注目 - 「リーダーシップを発揮した経験」
→ チームの中で自ら動いた経験や、メンバーとの関わりが重要 - 「変化にどう対応したか」
→ 柔軟性や対応力を示す機会
すべての質問にSTAR構造で答える必要はありませんが、「説明 → 具体例 → 結論」の流れを意識することで、より論理的に伝わります。
3.面接官が重視する評価基準

3.1 行動特性とリーダーシップの評価
面接官は「その人が過去にどのような行動をとってきたか」だけでなく、それを今後の職場で「再現できるかどうか」に着目しています。特にリーダーシップの評価では、以下のようなポイントが見られます。
- 他者に影響を与えた経験
- 問題発見から解決までの道筋
- 困難に直面した際の自己統制
リーダーシップは「役職」ではなく「行動」であり、新卒でも十分評価対象となります。
3.2 業績との関連性・スキルの見極め
評価基準は、単なる印象や態度ではなく、企業の中で成果を出せる行動特性にリンクしています。
以下のような点が見極めの焦点となります。
| 項目 | 見極めの視点 |
| 課題解決力 | 論点の整理、解決アプローチの妥当性 |
| 継続性 | 諦めずに行動した履歴 |
| 忍耐力 | ストレス下での冷静な判断 |
| 顧客志向 | 利害関係者への配慮と信頼構築 |
つまり、「できるかどうか」ではなく、「これまでやってきたかどうか」に重きを置くのが、コンピテンシー面接の特徴です。
3.3 評価基準を理解するためのフレームワーク
多くの企業では以下のようなフレームワークを導入して、コンピテンシーの整理と評価を行っています。
- Lomingerコンピテンシー :全世界で使われている61項目の行動特性定義
- 社会人基礎力(経済産業省) :前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力
- 企業独自の人材要件マトリクス:たとえば「誠実性 × 主体性」などを軸に評価
フレームワークを活用することで、面接官間の評価のズレを最小限に抑えることができます。
4.候補者の行動を探るための手順
4.1 面接の準備から実施のステップ
コンピテンシー面接は即興では成立しません。面接官・候補者ともに、事前の準備が大切です。以下に面接準備から実施までの一般的なステップを紹介します。
【面接官側の準備ステップ】
- 必要なコンピテンシーの選定
採用したい職種に応じて「求める行動特性」を明確化(例:課題解決力・主体性・協調性) - 評価シートの作成
質問項目と評価軸を整理。できれば具体的な行動レベル(例:自ら提案する、周囲を巻き込む等)を明記。 - 質問の構築(STARをベースに)
例:「困難な状況をどう乗り越えましたか?」→S・T・A・Rに分けて深掘りする。 - 評価ルーブリックの共有
面接官が複数いる場合は評価基準を共有し、バイアスを避ける。
候補者側の準備ステップ
コンピテンシー面接で高評価を得るためには、事前の綿密な準備が欠かせません。ここでは、候補者が面接本番に備えるための具体的な4つのステップについて詳しく解説します。
4.2 自己分析と経験の棚卸し
まずは自分自身の過去の経験を振り返り、応募する職種に関連する行動エピソードを洗い出しましょう。学業やアルバイト、部活動、インターンシップ、ボランティア活動、趣味のプロジェクトなど、人生の中で何らかの形で自分が主体的に関わった出来事はすべて対象になります。
- ポイントは「行動」に注目すること
ただ単に「○○をやりました」という表面的な内容ではなく、「自分がその場でどのように考え、どんな行動をとったのか」を意識しましょう。 - 5~10個程度のエピソードを用意する
面接では質問内容が多岐にわたるため、複数のシチュエーションを持っておくと安心です。たとえば「チームでの課題解決」「困難な状況での対応」「リーダーシップを発揮した経験」など、多様な角度から準備をしましょう。 - 成功体験だけでなく、失敗や苦労した経験も重要
失敗から何を学び、どう改善したかを話せる人は、成長意欲や柔軟性をアピールできます。 - 書き出しで視覚化すると効果的
ノートやExcelなどに「いつ・どこで・何を・どうしたか」を整理していくと、自分の経験が客観的に見えてきます。
4.3 STAR形式でエピソードを言語化
次に、自己分析で洗い出したエピソードを、STARモデルのフレームワークに沿って言語化していきます。
- Situation(状況)
どんな背景や環境だったのか、読んだ人が状況をイメージできるように具体的に説明することが重要です。 - Task(課題)
その状況下で自分にどんな役割や責任があったのか明確に示します。 - Action(行動)
最も重要な部分。自分がどのような行動を取ったのか、具体的に詳細に説明します。できれば「なぜその行動を選んだのか」も加えると説得力が増します。 - Result(結果)
その結果としてどんな成果が得られたのか、数値や第三者の評価など、できるだけ客観的な指標を示すと良いでしょう。 - メモ程度でも構わないので、書き出すことが大切
言葉にすることで頭の中が整理され、面接時にも自信を持って話せます。 - 複数パターンで練習することもおすすめ
同じエピソードでも強調点を変えると、質問に応じた柔軟な回答が可能になります。

4.4 企業の求める人物像を把握
企業ごとに求める人物像や重視するコンピテンシーは異なります。そのため、応募先企業の情報収集も欠かせません。
- 企業の公式採用ページや募集要項を詳細にチェック
企業理念、ビジョン、求める人材像、職務内容に記載されているキーワードは必ず確認しましょう。 - 企業の業界特性や競合他社との違いも理解する
これにより、企業が特に重要視する能力や価値観が見えてきます。 - 求人広告や企業のSNS、ニュースリリースを活用
最新の動向や社風を掴み、面接時に話題として織り込むことも効果的です。 - 必要なコンピテンシーを読み取り、自己エピソードと結びつける
たとえば「チームワーク」を重視する企業であれば、その経験を多めに準備し、「顧客対応力」が求められるならその分野のエピソードを掘り下げるなど、対策の精度を高めましょう。
4.5 模擬練習の実施
最後は、実際の面接を想定した模擬練習で実践力を磨きます。
- 家族や友人、大学のキャリアセンターの担当者に面接官役をお願いする
本番の緊張感に近い環境で練習することで、質問への受け答えがスムーズになります。 - 質問に対してSTAR形式で回答する練習を繰り返す
回答が長すぎたり短すぎたりしないよう、論理的かつ簡潔に話すことを意識しましょう。 - 録音や録画を活用し、自分の話し方や表情を客観的にチェック
言葉遣いや声のトーン、話す速度など、改善点を見つけて次に活かせます。 - フィードバックを受けて改善を重ねることが重要
他者からの意見を素直に受け入れ、必要に応じて回答内容や伝え方をブラッシュアップしましょう。 - オンライン面接の練習も忘れずに
最近はオンライン面接が増えています。ネット環境やカメラ映り、背景の整理なども事前に確認し、慣れておくことが安心感につながります。
4.6 フィードバックループの活用と課題解決
面接後には、以下のような「フィードバックループ」を設けることが推奨されます(企業側でも個人でも)
- 企業側:
- 候補者の回答を記録し、複数面接官でのフィードバックを交差検証
- 面接内容と採用後の活躍度の相関を測定し、評価軸をブラッシュアップ
- 候補者側:
- 面接後に自己評価を実施。「STARに沿って話せたか?」「結果まで言えたか?」
- できれば録音・録画をして振り返り(模擬練習でも有効)
このフィードバックを通して、回数を重ねるごとに「より深く、的確な行動説明」ができるようになります。
4.7 評価シートによる客観的な判断
以下は、実際に使われる評価シートの一例です(例:リーダーシップ評価の場合)。
| 評価項目 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
| 主体性 | 指示待ちが多い | 指示に対して行動 | 自ら改善案を出す | 周囲を巻き込んで 変革 |
| 問題解決 | 対処に時間がかかる | 解決に向けて努力 | 解決策を導く | 抜本的な改善まで 導く |
| 対人関係 | 一定のコミュニケーション | 周囲と円滑に協働 | 信頼を築く | 対立を調整・解決 する |
評価シートは数値化だけでなく、面接官の主観を整理するためにも重要なツールです。候補者も「このような視点で見られている」ことを理解すると、対策がしやすくなります。
5.コンピテンシー面接の導入と実践

5.1 企業における導入事例と効果
近年では、大手企業から中小企業、官公庁にいたるまで、幅広い領域でコンピテンシー面接が導入されています。いくつかの事例を紹介します。
事例1:NTTグループ(新卒・中途採用)
- 導入背景:形式的な「志望動機」より、行動に裏打ちされた能力を重視
- 結果:入社後の定着率が向上し、離職率が1年以内に2.5%改善
事例2:ソニーグループ(技術職採用)
- STAR形式でのポートフォリオ提出を推奨
- 行動+成果が分かるプレゼン評価によって「論理的な提案力」を見極めやすく
事例3:地方自治体(公務員試験)
- 民間の評価手法を積極的に導入
- 「形式ではなく本質で勝負できる面接」へと転換し、多様な人材の獲得に成功
トレーニングとリソースの重要性
企業がコンピテンシー面接を正しく導入・運用するには、面接官のトレーニングが必須です。
- 社内研修:STARモデルを理解し、行動を深掘る技術を磨く
- マニュアル整備:質問集・評価基準・判定ルーブリックなど
- ロールプレイ実施:実際の模擬面接でフィードバックを行う
候補者側も、以下のリソースを活用して準備を行うとよいでしょう。
- 大学のキャリアセンター
- 転職エージェントの面接対策講座
- 書籍・Web記事による事例研究
- ChatGPTのようなAIとの模擬面接練習も有効
6.新卒、中途、公務員、各職種への適用
6.1 各職種におけるコンピテンシーの違い
コンピテンシー面接は職種によって評価のポイントが変わります。新卒、中途、公務員といった属性でも求められる行動特性は異なります。
- 新卒
- 主に「ポテンシャル」と「行動特性」を評価
- まだ実務経験がないため、「学習意欲」「主体性」「協調性」などの基礎力が重視される
- 中途採用
- 即戦力を求められるため、「専門スキル」「問題解決力」「リーダーシップ」など具体的成果が問われる
- 過去の業務経験から得た行動パターンを重視
- 公務員
- 公共性・倫理観・公平性が最重要視される
- 「チームワーク」「課題解決」「説明責任」などの行動特性が評価されやすい
また、業界や職種別にも重要視されるコンピテンシーは異なります。
| 職種例 | 重要視されるコンピテンシー |
| 営業職 | 顧客志向、コミュニケーション能力、交渉力 |
| 技術職 | 論理的思考力、問題解決力、継続学習力 |
| 管理職 | リーダーシップ、意思決定力、対人調整力 |
| 事務職 | 正確性、計画性、協調性 |
6.2 人気の職種別コンピテンシー面接対策
営業職の場合
- 顧客のニーズを把握し、それに応じた提案ができるエピソードを準備
- 困難な交渉を成功させた経験や目標達成のための工夫をSTARで語る
技術職の場合
- 複雑な問題に直面した際の分析・解決方法を具体的に説明
- チームでの役割や知識習得の努力も評価ポイント
管理職の場合
- 部下の育成やチームの士気向上に貢献したエピソード
- 組織課題を解決し、成果に結びつけた具体例
公務員の場合
- 公共の利益を意識した行動や倫理観を示す体験
- 多様な利害関係者との調整・合意形成の経験
7.注意すべきポイントと一般的なミスマッチ

7.1 具体的な課題と成功の鍵
コンピテンシー面接でありがちな課題は以下の通りです。
- 準備不足によるエピソードの薄さ
→ 実例を多く準備し、STARで話す練習を繰り返すことが重要 - 話が抽象的で具体性に欠ける
→ 数字や事実、成果を必ず盛り込む - 結果だけを話して過程が曖昧
→ 「A(行動)」の部分に焦点を置き、何をどうやったかを詳述 - 面接官の質問意図を誤解する
→ 質問の意図を確認し、深掘りが必要なら聞き返す勇気も大切
成功の鍵は「準備」「論理的に話すこと」「誠実な態度」です。面接は相手とのコミュニケーションでもあるため、緊張してもリラックスして望みましょう。
7.2 自己PRとの関連性と考慮点
自己PRは自分の強みを伝える重要な機会ですが、コンピテンシー面接では「強みを裏付ける具体的行動」が求められます。
- 自己PRはSTARモデルの「A(行動)」と「R(結果)」を簡潔にまとめたもの
- 単なる抽象的な言葉(例:「私は責任感があります」)ではなく、裏付けとなる行動と成果を語る
また、自己PRの内容が面接中の質問と整合しているかも大切です。一貫性のある話し方が信頼感を生みます。
8.最後に・・・
コンピテンシー面接を制するために今できること
現代の採用現場において、コンピテンシー面接は単なる流行の手法ではなく、企業が「本当に活躍できる人材」を見極めるための重要な評価基準となっています。これまでのように、表面的な受け答えや自己アピールの巧拙だけではなく、「過去の具体的な行動」と「その行動から得られた成果や学び」に基づいて判断されるため、求職者の真の能力や資質がより公正に評価されるようになりました。
これからの就職・転職活動においては、単に面接を受けるだけではなく、「自己理解の深化」と「具体的な行動エピソードの整理」が不可欠です。つまり、日常の経験や仕事の中でどのように課題に取り組み、どんな結果を出してきたかを振り返り、言語化できる力が求められています。この力は一朝一夕に身につくものではなく、継続的な自己分析と練習を通じて磨かれるものです。
さらに、AI面接やオンライン面接の普及により、面接の形式や評価基準も多様化していくことが予想されます。映像を通じた非言語コミュニケーションの観察、AIによる言語解析など、テクノロジーの介入が進む中でも、自分の「行動に裏付けられた実績」と「誠実な自己表現」は決して色褪せることはありません。むしろ、多面的に評価される環境だからこそ、しっかりとした準備と自信を持って臨むことが大きなアドバンテージとなります。
そして何より、コンピテンシー面接の準備は「自分のキャリアを深く見つめ直し、これからの成長や方向性を考える絶好の機会」でもあります。単なる面接対策として捉えるのではなく、自分自身の強みや課題を客観的に理解し、未来に活かすための自己成長プロセスと捉えることで、面接の場が単なる通過点ではなく、キャリアの重要なステップとなるでしょう。
最後に、成功の秘訣は「準備」と「継続」です。焦らず着実に自己分析を深め、STARモデルでの表現力を磨き、模擬練習やフィードバックを重ねることで、必ず面接本番でのパフォーマンスは向上します。どんなに厳しい質問が来ても、自分の過去の行動と成果に自信を持って臨むことで、面接官に確かな印象を残すことができます。
今後も変化し続ける採用環境の中で、自分の強みを最大限に発揮し、納得のいくキャリアを築くために、ぜひこのコンピテンシー面接のノウハウを活用してください。株式会社S.I.Dはそんな皆さんこれからも採用支援をしていきます。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
皆さんの成功を心よりお祈り申し上げます。