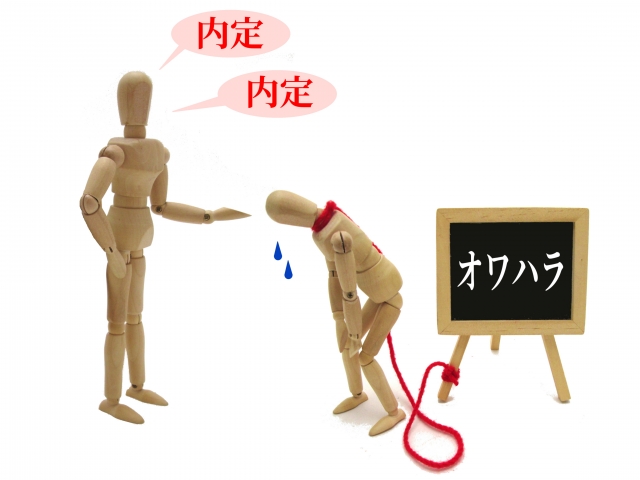目次
1.内定後の“オワハラ”とは?その実態を知る
2.企業側から見た「オワハラ」が発生する要因
3.オワハラの具体例とケーススタディ
4.内定承諾のリスクとトラブル
5.「オワハラ」を避けるための判断力
6.就活生が知っておくべき対策
7.内定後の判断力を高める方法
8.オワハラに関するよくある質問(Q&A)
9.最後に・・・
1.内定後の“オワハラ”とは?その実態を知る

1.1 オワハラの定義と背景
2015年7月頃から就職活動において「オワハラ」という言葉が使われはじめました。就活生や転職活動をされたことのある皆さんも1度は聞いたことがあるのでないでしょうか。オワハラとは「就活終われハラスメント」の略で、企業が学生や転職者に対し「もう他社の選考を受けるな」「うちの内定を承諾して就活を終わらせろ」と強く迫る行為を指します。表向きは「会社に対する熱意を確認するため」や「内定辞退を防ぐため」といった建前を用いるケースが多いですが、実際には過度な圧力や脅迫に近い対応が行われることも少なくありません。
背景としては、日本の新卒一括採用文化や、中途採用市場における人材獲得競争の激化が挙げられます。特に人材不足の業界では、せっかく確保した人材を他社に奪われたくないという企業の焦りが強く、その結果としてオワハラが増加しているのです。
1.2 増加するオワハラの実態
近年の就職・転職市場を見渡すと、SNSや掲示板には「内定先から強引に就活をやめろと言われた」「内定辞退を考えたら脅迫めいた発言を受けた」といった声が多数寄せられています。企業側にしてみれば人材獲得競争が激しくなり、特に優秀な人材を確保するためには手段を選ばなくなっているのが現状です。
大学キャリアセンターや労働相談窓口への相談件数も増加しており、オワハラが一時的なトレンドではなく構造的な問題になっていることが浮き彫りになっています。
2.企業側から見た「オワハラ」が発生する要因

2.1 採用競争の激化と人材不足
近年の採用市場は、業界を問わず人材獲得競争が激化しています。特に少子化の影響により、新卒採用では学生の数そのものが減少しており、優秀な人材を確保することは年々難しくなっています。中途採用市場においても、専門スキルを持つ人材は引く手あまたで、企業は常にライバル会社との競争にさらされています。
こうした背景から、一度内定を出した人材を「絶対に他社に渡したくない」という思いが強まり、結果として就活生・転職者に対して「就活をやめてほしい」という圧力をかける行為につながってしまいます。
2.2 採用コストの高さ
企業が一人の人材を採用するためには、求人広告、説明会、選考、面接、適性検査など、多額の費用と労力が投じられています。とくに大企業では年間の採用予算が数億円規模に上ることもあります。
そのため、せっかく投資をして選抜した人材が辞退してしまうと「コストが無駄になった」という強いプレッシャーを感じます。採用担当者や人事部門は上層部から「内定後の辞退率を下げろ」という圧力を受けることが多く、その焦りがオワハラにつながるのです。
2.3 内定辞退率を下げたいという組織的な思惑
企業はあらかじめ採用目標人数を設定し、それに基づいて採用活動を進めます。しかし、内定辞退が多く発生すると、計画通りの人数を確保できず、現場で深刻な人手不足を招く恐れがあります。
例えば、営業職で30人の採用を予定していたにもかかわらず、辞退が相次いで20人しか入社しなかった場合、翌年度の売上計画や事業展開にまで影響が及びます。
実際に、大手企業の中には毎年入社日当日に無断で辞退されるケースがありその結果、この5年間にわたって毎年10名単位の採用不足が生じている例もあります。
こうしたリスクを避けるため、企業は「内定辞退率を下げる」ことに強い関心を持ち、ときには強引ともいえる対応に出ることもあります。
2.4 社風や採用文化の影響
オワハラは企業文化そのものが影響している場合も少なくありません。たとえば「会社への忠誠心」を重視する古い体質の企業や、「採用は会社にとっての戦争だ」と考える体育会系の企業風土では、内定者に対しても強いコントロールをかける傾向があります。
また、採用担当者自身が過去に同じような教育を受けてきた場合、「自分もこうされたから当然だ」という感覚で内定者に圧力をかけてしまうケースも見られます。
2.5 採用担当者の評価制度
人事部や採用担当者は「採用人数」「辞退率」などの数値で評価されることが多いです。そのため、目標を達成できないと自らの評価や昇進にも影響します。結果として、担当者が必死になり、内定者に強い言葉を使ってでも就活を終わらせようとする動きにつながります。
つまり、オワハラは担当者の「個人的な悪意」というより、組織的な評価制度やプレッシャーの結果 である場合が多いのです。
🔍 このように「オワハラ」は、単なる担当者の気まぐれではなく、採用市場の競争、コスト、組織の事情、文化的背景などが複雑に絡み合って生じています。
就活生・転職者にとっては迷惑極まりない行為ですが、その背景を理解しておくことで「これは企業の都合で言っていることだ」と冷静に受け止めやすくなり、精神的に追い詰められにくくなります。
3.オワハラの具体例とケーススタディ

3.1 実際のオワハラ事例
- 内定式後に呼び出され「もう他社を受ける必要はないよね?」と暗に圧力をかけられる。
- 内定承諾書の提出を執拗に迫られ、提出しなければ内定を取り消すと脅される。
- 「君の就活は終わった」と繰り返し言われ、心理的に追い込まれる。
- 内定者懇親会で「他社を受けている人は裏切り者だ」と言われた。
3.2 2chやSNSでの報告内容
匿名掲示板やSNSには「オワハラに遭った」というリアルな体験談が溢れています。特に多いのは以下の声です。
- 「承諾書を書かないと次の選考に進めないと言われた」
- 「就活をやめないなら内定を取り消すと脅された」
- 「電話やメールで毎日のように承諾を迫られた」
これらの声は誇張ではなく、実際に多くの就活生や転職者が体験している現実です。
3.3 企業名別のオワハラ事件
報道ベースでは、某大手メーカーや人材会社、さらには地方銀行など、さまざまな業種でオワハラ事例が明らかになっています。特に競争率の高い業界や慢性的な人材不足の業界において、こうした事件が起こりやすい傾向にあります。
4.内定承諾のリスクとトラブル

4.1 内定承諾書に関する注意点
内定承諾書は法的拘束力を持つ契約書ではありませんが、提出してしまうと心理的には「もう辞退できない」と感じてしまう人が多いです。企業もそれを狙って提出を迫るケースがあります。
4.2 内定辞退の理由とその影響
実際に辞退する際には「他社の方が自分に合っている」「勤務地や待遇が合わない」といった理由が多く挙げられます。辞退そのものは自由ですが、伝え方を間違えるとトラブルに発展するリスクもあります。紹介会社からの求人の場合、トラブルを避ける意味でも断りづらかったらキャリアカウンセラーを通じてお断りすることをお薦めします。
4.3 オワハラによる脅迫の可能性
悪質な場合は「辞退したら大学に言う」「違約金を請求する」といった脅迫めいた言葉をかけられることもあります。これらは違法であり、法的根拠がないことを知っておくことが重要です。
5.「オワハラ」を避けるための判断力

5.1 オワハラ系の企業を見抜く方法
- 面接中に「就活を続けますか?」と何度も確認してくる。
- 内定を出す前から承諾を急かす。
- 学校やエージェントを巻き込んで囲い込もうとする。
こうしたサインがあれば、オワハラ体質の企業である可能性が高いです。
5.2 答え方や対応の実例
「現時点では御社に強い関心がありますが、他社も含めて検討中です」と答えるのが基本です。過度に隠す必要はありませんが、正直に伝えすぎて不利益を被らないよう注意しましょう。
5.3 必要な自己防衛スキル
- 法律知識を持っておく。
- 相談できる人(大学キャリアセンター、労働局、弁護士)を確保する。
- 記録(メールや会話のメモ)を残す。
6.就活生が知っておくべき対策

6.1 オワハラ防止のための基本知識
まず大切なのは「知っているかどうか」です。多くの就活生が不安を抱える原因の一つは、内定後に企業から強い言葉をかけられたとき、「本当に断れないのではないか」「法律的に違反してしまうのではないか」と誤解してしまう点にあります。
しかし、実際には 「内定承諾を強制することはできない」 のが法律上の原則です。内定承諾書や誓約書にサインをしたとしても、それは必ずしも法的拘束力を持つ契約とはみなされません。もちろん、企業によっては「承諾した以上、誠実さに欠ける」といった倫理的な言葉で責めてくる場合もありますが、法的に罰せられるものではないのです。
また、まれに「辞退したら違約金を請求する」と言われるケースもあります。しかし、労働契約法や判例の考え方から見ても、内定辞退に違約金を課すことは原則として無効 です。仮に契約書にそのような条項があったとしても、公序良俗に反する無効な規定となるため、恐れる必要はありません。
このような基礎知識を持っているかどうかで、オワハラに遭遇した際の心の持ち方が大きく変わります。知識がなければ「もしかして本当に訴えられるのでは…」と萎縮してしまいますが、正しく理解していれば「これは不当な要求だ」と冷静に対応できます。
6.2 企業とのコミュニケーション術
オワハラに直面したとき、多くの就活生が陥りやすいのは「感情的に反応してしまう」ことです。例えば、強く迫られると反発してしまい、思わずきつい言葉で返してしまうケースがあります。しかし、感情的なやり取りは状況を悪化させ、トラブルに発展する危険性を高めます。
重要なのは 冷静かつ丁寧に対応する姿勢 です。企業にとっても、あなたが本当に内定を承諾してくれるのか不安があるからこそ強く出ている場合が多いため、その心理を理解したうえで対処するのが賢明です。
具体的な対応例としては以下のような方法があります。
- 「検討の上、○月○日までにお返事いたします」
→ 回答の期限を自分で設定し、相手にも明確に伝えることでプレッシャーを軽減できます。
- 「御社に強い関心を持っていますが、他社も含めて検討を続けています」
→ 嘘をつかずに正直な立場を示しながらも、結論を急がせない対応が可能です。
- 「今後のスケジュールについて整理した上で、必ずご連絡します」
→ 相手に誠実さを伝えつつ、余裕を確保する言い回しです。
また、対面や電話で圧力をかけられた場合には、その場で即答せず「持ち帰って考えたい」と伝えることも有効です。焦ってその場で承諾してしまうと後で取り返しがつかなくなるため、「一度冷静に考える時間を持つ」という姿勢を徹底しましょう。
6.3 信頼できるエージェントの利用
最後に強調したいのが、一人で抱え込まないこと です。オワハラの厄介な点は、相手が企業という立場上「断ることが難しい」と感じやすいことにあります。そのため、孤立して対応していると精神的に追い詰められやすくなります。
そこで活用したいのが 転職エージェントや大学キャリアセンター です。エージェントは採用担当者とのやり取りに慣れており、求職者に代わって企業と交渉してくれることもあります。大学キャリアセンターもまた、学生が不利な立場に立たされないよう支援してくれる専門機関です。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 交渉の盾になってくれる
「内定承諾を急かされて困っている」と相談すれば、あなたの代わりに企業に確認してくれる場合があります。 - 客観的な意見がもらえる
「この会社は強引すぎる」「もう少し待った方がいい」など、第三者の視点でアドバイスを受けられます。 - 精神的な安心感が得られる
一人で悩むのではなく、専門家に支えられているというだけでも大きな心の支えになります。
特に転職市場では、エージェントを介して応募している場合、企業が直接オワハラを仕掛けにくくなる傾向があります。なぜなら、エージェントが間に入っているため、不当な圧力が可視化されやすくなるからです。
「自分一人で何とかしなければ」と考えず、信頼できるサポーターを積極的に活用することが、オワハラから身を守るうえで極めて重要なポイントといえます。
✅ 以上の3点を押さえておけば、オワハラに直面したとしても冷静に判断でき、トラブルを最小限に抑えられます。
7.内定後の判断力を高める方法
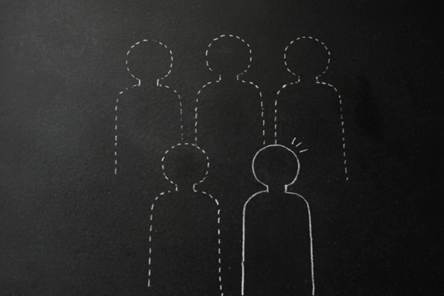
7.1 キャリア選択の重要性
就活・転職活動はゴールではなく、スタート地点です。オワハラに屈して妥協した選択をしてしまうと、その後のキャリアに長期的な影響を及ぼします。
7.2 内定後の行動計画の立て方
- 他社選考のスケジュールを明確に管理する。
- 内定承諾の期限を確認し、無理に即答しない。
- 家族やキャリア相談機関と話し合う。
7.3 内定者同士の情報共有の利点
同じ企業の内定者同士でつながると、オワハラの有無や対応の仕方について情報を交換でき孤立感を防ぐことができます。
8.オワハラに関するよくある質問(Q&A)

Q. オワハラは法律でどう扱われるのか?
A. オワハラ自体を直接規制する法律はありませんが、脅迫や強要に該当する場合は刑法違反となる可能性があります。
また、労働契約に関する不当な扱いとして民事トラブルに発展することもあります。
Q. オワハラの相談先について、どこに相談したらいいの?
A.無料・有料での対応とありますので事前に電話・メールにてアポイントを取ってから相談に行くことをお薦めします。
- 大学キャリアセンター
- 労働局の総合労働相談コーナー
- 弁護士や労働組合
いずれも無料で相談できるケースが多いため、早めに活用することが大切です。
Q. 他社の内定と併用するリスクは?
A.複数の内定を保持すること自体は違法ではありません。ただし承諾を曖昧にしたまま放置するとトラブルに
つながるため、誠意を持って対応する必要があります。
9.最後に・・・
オワハラは就活生・転職者にとって深刻な問題ですが、知識と判断力を持てば冷静に対応できます。企業にとっても採用は大きな投資である一方、求職者にとっては人生の方向性を決める重要な選択です。オワハラに屈して「不本意な入社」を選ぶのではなく、自分のキャリアに最も適した道を選ぶことが大切です。
それでも不安や迷いが強い場合は、大学のキャリアセンターや転職エージェント、労働局、弁護士といった専門機関に相談するのも一つの手です。孤独に戦う必要はありません。情報を正しく持ち、支援を受けながら、自分にとってベストなキャリアの第一歩を踏み出していきましょう。
株式会社S.I.Dは専任のキャリアカウンセラーが常駐しております。
▶【株式会社S.I.Dのお仕事検索 はこちら】
▶【株式会社S.I.D ご相談窓口 はこちら】
自分のキャリアに最も適した道を選ぶことが大切です。